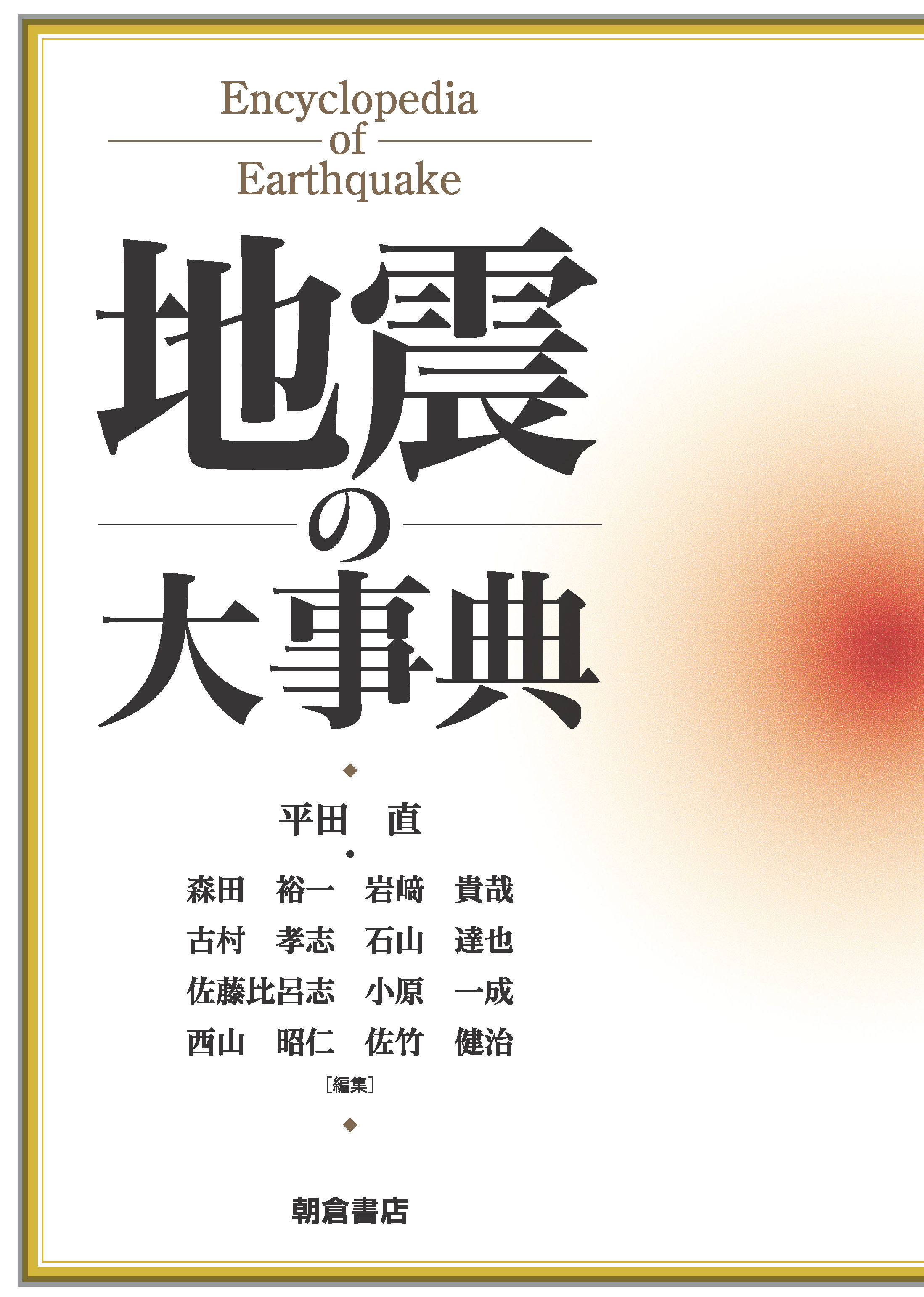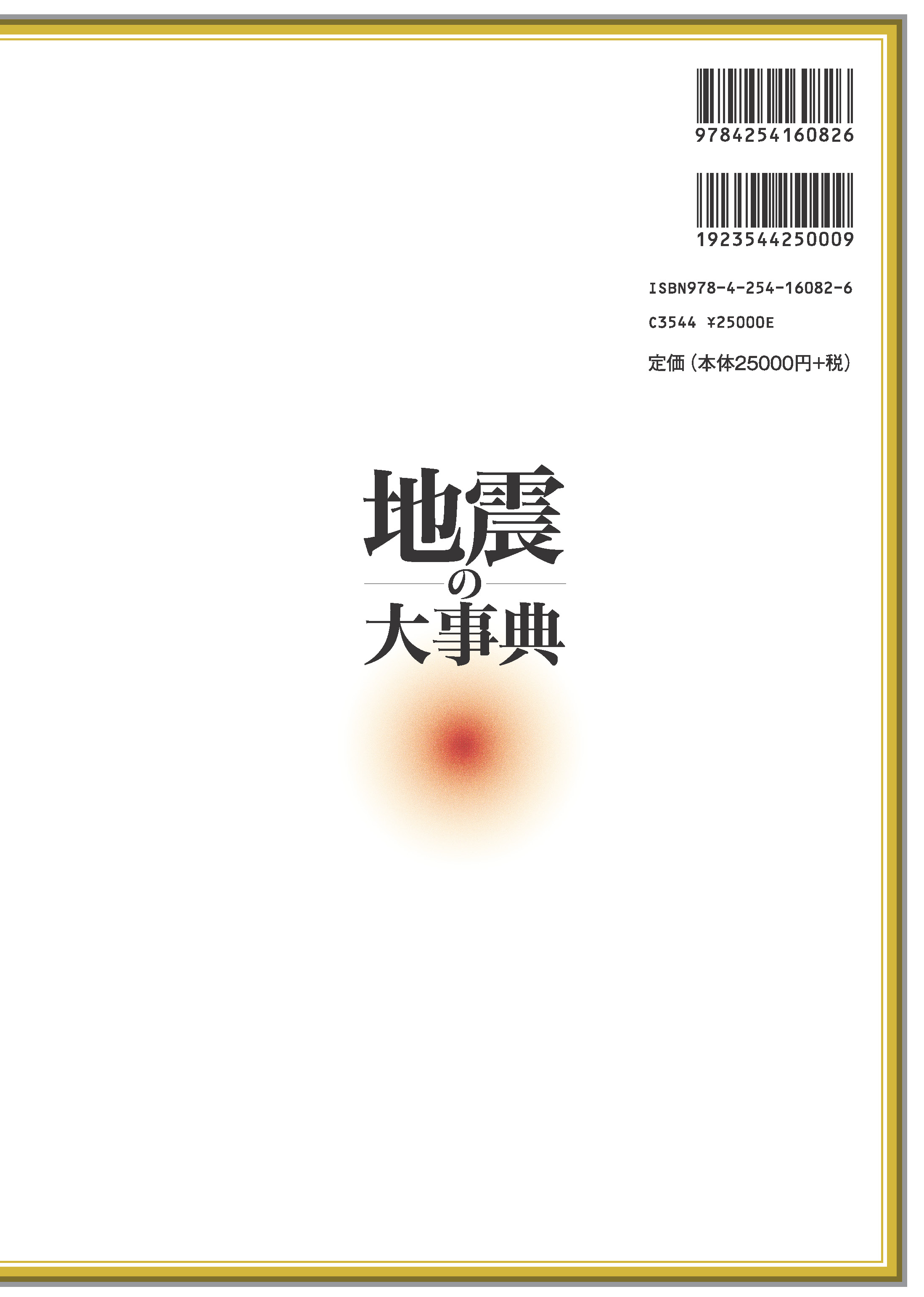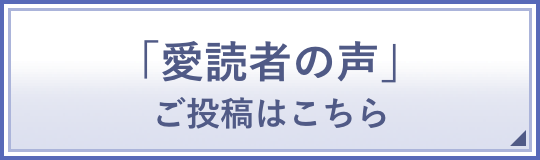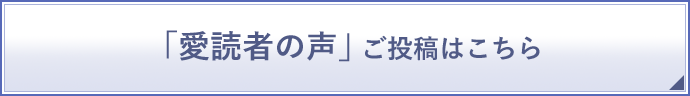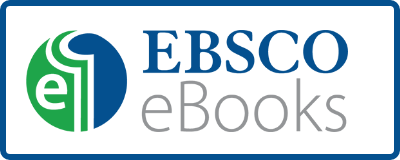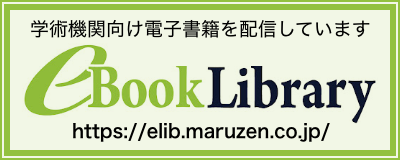BOOK SEARCH
地震の大事典
内容紹介
地震の仕組みとメカニズムを解説する総合事典。地震学の定本と評された旧版以降の,スマトラ大地震,東北地方太平洋沖地震,熊本地震などの研究成果を踏まえて全面的に内容を一新。〔内容〕地殻変動の観測/地震波の伝播/地震活動の性質/プレートテクトニクス/プレートの沈み込み/内陸の地震/古地震/巨大地震/地震詳細年表
編集部から
目次
1.地 震 の 概 観〔平田直〕
1.1 地震,地震動,震災
1.2 地震とは─震源断層の形成─
1.3 地震と地震動
1.3.1 地震波
1.3.2 地震動
1.4 地震の原因(地震を起こす力)
1.5 地震の時間的分布
1.5.1 地震が起きる場所:地震はどこで起きるか─地震の空間的分布─
1.5.2 地震の時間的分布
1.6 地震の大きさ
1.7 地震発生の予測
1.7.1 統計的予測
1.7.2 決定論的予測
1.8 地震動予測
1.9 地震災害の予測と被害想定
2.地震と地殻変動の観測〔森田裕一〕
2.1 地震計の原理と各種地震計 〔森田裕一〕
2.1.1 地震計の歴史
2.1.2 機械式地震計─地震計の力学的機構─
2.1.3 電磁式地震計─地震動の電気信号化─
2.1.4 振り子の制御─負帰還回路の応用─
2.1.5 加速度計・強震計─変位帰還型地震計─
2.1.6 広帯域地震計─ PID 帰還型地震計─
2.2 地震観測網
2.2.1 地震観測網を構成する地震観測点〔森田裕一〕
a.地震計の設置方法
b.データ伝送・記録装置
c.地震計,観測システムの周波数特性の記述
2.2.2 地震観測網の種類
2.2.3 高感度地震観測網 Hi-net〔汐見勝彦〕
2.2.4 強震観測網 K-NET/KiK-net
2.2.5 広帯域地震観測網 F-net
2.3 地震観測のノイズ〔森田裕一〕
2.3.1 地動ノイズ
a.雑微動
b.脈動
2.3.2 地震計のノイズ
2.3.3 海底地震計のノイズ〔篠原雅尚〕
2.4 地殻変動観測〔三浦哲〕
2.4.1 測 地 測 量
a.辺長測量
b.水準測量
2.4.2 地殻変動連続観測
a.坑道内のひずみ・傾斜観測
b.孔井内のひずみ・傾斜観測
2.4.3 GNSS による地殻変動観測
a.GPS による単独測位
b.搬送波位相を用いた高精度測位
c.実際の GNSS観測
2.4.4 SAR による地殻変動観測
a.SAR の原理
b.SAR 衛星
c.干渉 SAR の解析事例
2.5 海 底 観 測〔篠原雅尚〕
2.5.1 自己浮上式海底地震計
2.5.2 ケーブル式海底地震計
2.5.3 海底地殻変動観測
3.地震波の伝播・地震性地殻変形の理論〔岩﨑貴哉・古村孝志〕
3.1 弾性体力学の基礎〔岩﨑貴哉〕
3.1.1 ひずみと応力
a.弾性体の表記法
b.ひずみ
3.1.2 弾性体力学の基礎方程式
a.質量保存則と連続の式
b.運動方程式と応力
c.角運動量および力のモーメント
d.主ひずみ,偏差ひずみと主応力,偏差応力
3.1.3 構成式
3.1.4 一意性の定理と相反定理
a.一 意 性 の 定 理
b.相 反 定 理
c.グリーン関数(テンソル)とその相反性
d.表現定理
3.2 弾 性 波 動〔岩﨑貴哉〕
3.2.1 運動方程式の解と波動方程式
3.2.2 平面波
3.2.3 平面波の伝播
a.P 波,SV 波と SH 波
b.自由表面での反射
c.固体-固体境界での反射と透過
3.2.4 指数関数的波動と表面波
a.自由表面における P-SV 波
b.固体-固体境界における SH 波
c.レイリー波
d.ラブ波
3.2.5 非弾性による減衰
3.2.6 地震波の発生
a.実体波の発生
b.表面波の発生
c.カニアル・ド・フープ法
d.反射率法
3.2.7 不均質場での波動伝播 〔古村孝志〕
a.地震波伝播の差分法計算
b.モデルの離散化とスタガード格子
c.地震波伝播の陽的計算
d.自由表面の境界条件
e.無反射(吸収)境界条件
f.非弾性減衰(Q)の導入
3.3 波 線 理 論〔岩﨑貴哉〕
3.3.1 基礎方程式
3.3.2 アイコナル方程式とその応用
a.アイコナル方程式
b.フェルマーの原理と波線追跡法
c.水平構造の場合の走時
d.球対称構造モデル
3.3.3 輸送方程式とその応用
3.3.4 理論波形の計算
3.4 震源の力学モデル〔加藤尚之〕
3.4.1 点震源モデル
3.4.2 有限断層モデル
3.4.3 動的震源モデルと摩擦構成則
3.5 断層による静的・準静的変形〔佐藤利典〕
3.5.1 弾性体中の断層による変形
3.5.2 断層による準静的変形
a.粘弾性の表現方法
b.履歴積分
c.対応原理
d.断層による粘弾性変形
3.5.3 地震サイクルモデル
a.地震サイクルの運動学的表現.
b.沈み込み帯での地震サイクルによる地表変動
3.6 地震波解析理論とその応用
3.6.1 順問題と逆問題〔深畑幸俊〕
3.6.2 震 源 決 定〔加藤愛太郎〕
3.6.3 地震波を用いた地球内部構造推定
a.制御震源地震探査の解析 〔岩﨑貴哉〕
b.地震波とトモグラフィ 〔加藤愛太郎〕
c.レシーバ関数法 〔西田究・利根川貴志〕
d.地震波干渉法
3.6.4 震源過程の推定〔深畑幸俊・八木勇治〕
a.モーメントテンソルインバージョン
b.破 壊 過 程 の 推 定
c.測 地 イ ンバージョン
4.地震の起き方と地震活動の性質〔平田直〕
4.1 地震の大きさと(\(M\))と頻度〔鶴岡弘〕
4.1.1 地震の大きさ
a.表面波マグニチュード \(M s\)
b.実体 波 マ グ ニ チ ュ ー ド \(m B \)
c.\(M s,M s,m B\) の関係
4.1.2 各種のマグニチュードの定義
a.基準となるマグニチュード
b.マグニチュードの式の形式
c.ISCと USGS のマグニチュード
d.気象庁のマグニチュード
e.微小時間のマグニチュード
f.地震動継続時間によるマグニチュード
g.モーメントマグニチュード
h.津波によるマグニチュード
i.震度によるマグニチュード
4.1.3 各種マグニチュードの特徴と問題点
4.2 断層モデルの相似則(スケーリング則)〔三宅弘恵〕
4.2.1 巨視的断層パラメター
4.2.2 微視的断層パラメター
4.2.3 地震カタログ
4.3 地震活動の時空間的性質〔勝俣啓〕
4.3.1 地震活動の空間的性質
4.3.2 地震活動の時間的性質
4.3.3 地震活動の時空間的性質
4.4 群れをなす地震─前震・本震・余震─〔加藤愛太郎〕
4.4.1 群発地震と前震・本震・余震
4.4.2 前震
4.4.3 余震
a.余震の統計的性質
b.震源断層近傍の余震と離れた余震,誘発地震
c.余震発生機構の物理モデル
4.5 地震発生時系列モデル〔鶴岡弘〕
4.5.1 点過程
4.5.2 ポアソン過程
4.5.3 BPT 過程
4.5.4 地震発生確率の計算方法
5.地震を発生させる場のテクトニクス〔佐藤比呂志・岩﨑貴哉・石山達也〕
5.1 プレートテクトニクスと地震活動・世界の変動帯〔石山達也〕
5.2 変動帯としての日本列島とそのプレート構造〔佐藤比呂志〕
5.2.1 日本列島に沈み込む海洋プレート
5.2.2 東北日本弧の構造とテクトニクス
5.2.3 千島弧と東北日本の会合部の構造とテクトニクス
5.2.4 関東の構造とテクトニクス
5.2.5 西南日本の構造
5.2.6 日本海の拡大様式
5.2.7 日本列島周辺の上盤プレート
5.3 日本列島の基盤構造〔伊藤谷生・佐藤比呂志・大藤茂〕
5.3.1 日本列島を構成する各弧の構造
a.西南日本弧
b.南西諸島弧(琉球弧)〔西澤あずさ〕
c.東北日本弧
d.千島弧
e.伊豆-小笠原弧〔高橋成実〕
5.3.2 日本列島の基盤構造を規定する主要な断層系
a.中央構造線
b.糸魚川-静岡構造線
c.日高主衝上断層および前縁褶曲・衝上断層帯
6.プレートの沈み込みに伴う地震〔小原一成〕
6.1 プレート境界面に発生する地震
6.1.1 メガスラスト(巨大衝上断層)地震〔谷岡勇市郎〕
a.巨大地震の発生様式
b.巨大地震の震源過程
6.1.2 巨大地震に伴う諸現象
a.地殻変動 〔加藤照之〕
b.余震〔岡田知己〕
c.誘発地震等の地殻活動 に 及 ぼ す 影 響
d.先 行 的 現 象〔加藤愛太郎〕
6.1.3 繰り返し地震─相似地震─〔内田直希〕
a.小繰り返し地震
b.釜石沖地震
6.1.4 プレート境界地震のモデル化〔堀高峰〕
a.アスペリティモデル
b.数値シミュレーション
6.2 スラブ内地震
6.2.1 深発地震・稍深発地震 〔中島淳一〕
a.世界の深発・稍深発地震震源分布の特徴
b.二重深発地震面
c.スラブ内地震の成因
6.2.2 アウターライズ地震〔日野亮太〕
a.ア ウ タ ー ラ イ ズ 地 震 の メ カ ニ ズ ム
b.プレート境界地震による誘発
6.3 スロー地震
6.3.1 スロー地震の概要と分類〔小原一成〕
6.3.2 スロースリップイベント〔廣瀬仁〕
a.断層クリープ
b.余効滑り
c.スロースリップイベント
d.他のスロー地震・地震との同時発生
e.大地震と関連する SSE
f.様々な地域の SSE
6.3.3 低周波微動〔小原一成〕
a.微動の検出と震源決定
b.低周波地震との関係
c.プレート沈み込み境界で発生する微動
d.プレートすれ違い境界で発生する微動
e.遠地地震による誘発微動
6.3.4 超低周波地震
a.深部超低周波地震 〔伊藤喜宏〕
b.浅部超低周波地震 〔浅野陽一〕
コラム:スロー地震と巨大地震との関連性〔小原一成〕
コラム:内陸の低周波地震の分布と発生メカニズム〔小菅正裕〕
7.内 陸 の 地 震〔佐藤比呂志・石山達也〕
7.1 日本の内陸地震の特徴
7.1.1 内陸地震の発生メカニズム─内陸地震の発生と地殻流体─〔加藤愛太郎〕
7.1.2 群 発 地 震〔酒井慎一〕
コラム:誘発地震〔酒井慎一〕
7.2 日本列島の内陸地震(年代順)
7.2.1 北海道地方〔佐藤比呂志〕
a.2018 年北海道胆振東部地震\(M j\) 6.7
7.2.2 東 北 地 方
a.2011 年福島県浜通りの地震 \(M\) 7.0 〔石山達也〕
b.2008 年岩手・宮城内陸地震 \(M\) 7.2 〔 越 谷信 〕
c.2004 年中 越 地 震 \(M\) 6.8,2007 年 中 越 沖 地 震 \(M\) 6.8 〔佐藤比呂志〕
d.2003 年宮城県北部 地 震 \(M\) 6.4( 1900 年 \(M\)<6.5, 1962 年 \(M\)6.5)〔佐藤比呂志〕
e.1914 年秋田仙北地震(強首地震)\(M\) 7.1 〔楮原京子〕
f.1896 年陸羽地震 \(M\) 7.2
g.1894 年庄内地震 \(M\) 7.0 〔松浦律子〕
7.2.3 日本海東縁部
a.1993 年北海道南西沖地震 \(M\) 7.8 〔岡村行信〕
b.1983 年日本海中部地震 \(M\)7.7 〔野徹雄〕
c.1964 年新潟地震 \(M\) 7.5 〔佐竹健治〕
d.1833 年天保出羽沖地震 \(M\) 7.6 〔松浦律子〕
7.2.4 関東地方と伊豆-小笠原弧
a.2000 年三宅島噴火に伴う群発地震活動〔酒井慎一〕
b.1978 年以降の伊豆東部の群発地震活動〔松浦律子〕
c.1974 年伊豆半島沖地震 \(M\) 6.9 〔松浦律子〕
d.1930 年北伊豆地震 \(M\) 7.3 〔道家涼介〕
7.2.5 中 部 地 方
a.2024 年能登半島地震→10.4.1 項を見よ
b.2007 年能登半島地震 \(M\) 6.9 〔佐藤比呂志〕
c.1965 年松代群発地震〔松浦律子〕
d.1948 年福井地震 \(M\)7.1 〔石山達也〕
e.1945 年三河地震 \(M\)6.8 〔杉戸信彦〕
f.1891 年濃尾地震 \(M\)8.0 → 10.4.3 項を見よ
g.1858 年安政飛越地震 \(M\)7.3 〔安江健一〕
h.1847 年善光寺地震 \(M\)7.4 〔佐藤比呂志・廣内大助〕
i.1586 年(1 月 16 日)天正地震 \(M\)7.8 〔石山達也・廣内大助〕
j.糸魚川-静岡構造線断層帯北部(2014 年長野県北部地震と過去の地震)〔佐藤比呂志〕
7.2.6 近 畿 地 方
a.1995 年兵庫県南部地震 \(M\)7.2 → 10.4.2 項を見よ
b.1927 年北丹後地震 \(M\)7.3 〔岡田真介・岡田篤正〕
c.1662 年寛文地震 \(M\)7.3 〔小松原琢〕
d.1596 年慶長伏見地震 \(M\)7.5〜8.0 〔寒川旭〕
e.1586 年(1 月 18 日)天正地震 \(M\)7.8 〔石山達也・廣内大助〕
7.2.7 日本海南西部
a.1872 年浜田地震 \(M\)7.0 〔松浦律子〕
7.2.8 中国・四国地方
a.2000 年鳥取県西部地震 \(M\)7.3 〔佐藤比呂志 〕
b.1943 年 鳥 取 地 震 \(M\)7.2 〔松多信尚・石山達哉〕
c.四国の中央構造線断層帯(1596 年文禄地震)〔堤浩之〕
d.山崎断層帯(868 年播磨国地震)〔松多信尚〕
7.2.9 九 州 地 方
a.2016 年熊本地震 \(M\)7.3 〔岩佐佳哉〕
b.2005 年福岡県西方沖地震 \(M\)7.0 〔松本聡〕
コラム:芸予地震と釧路沖地震〔松浦律子〕
8.地震による強い揺れ〔古村孝志〕
8.1 地震と強い揺れ(強震動)
8.1.1 断層運動と強震動〔三宅弘恵〕
8.1.2 揺れの増幅〔山中浩明〕
8.1.3 長周期地震動〔古村孝志〕
8.1.4 強震動の計測〔翠川三郎〕
a.震度階
b.強震観測
コラム:1〜4 g 超え加速度の観測〔青井真〕
8.2 強震動による建物の揺れ・被害
8.2.1 建物の揺れと被害〔楠浩一〕
8.2.2 耐震・免震構造
コラム:東北地方太平洋沖地震の強震動と建物被害〔翠川三郎〕
8.3 強震動による地盤災害・土砂災害
8.3.1 液状化現象〔安田進〕
コラム:近年の地震による液状化事例
8.3.2 地震による斜面崩壊〔土井一生〕
a.国内の地震による斜面崩壊事例
b.地震による斜面崩壊の素因
c.二次的な災害リスク
8.4 強震動の予測と被害推定
8.4.1 統計的グリーン関数・経験的グリーン関数による強震動計算〔三宅弘恵〕
8.4.2 動力学的モデルに基づく強震動シミュレーション〔吉見雅行〕
a.強震動計算のための動力学的モデル
b.断層破壊の不均質性
8.4.3 差分法等による理論的強震動計算〔青井真〕
コラム:スーパーコンピュータによる地震動シミュレーション〔古村孝志〕
a.支配方程式と定式化
b.境界条件
c.震源(断層型震源の表現法)
d.非弾性減衰(Q 値)
e.格子点間隔および安定性
8.4.4 強震動予測と地震被害想定〔翠川三郎〕
8.4.5 強震動予測のための地下構造探査〔山中浩明〕
8.4.6 地震津波予測シミュレーションの新しい取組み〔古村孝志〕
9.古地震〔西山昭仁〕
9.1 古地震の種類
9.1.1 歴 史 地 震〔西山昭仁〕
a.調査の時間範囲
b.調査の有効性と限界
c.成果の概要
9.1.2 地震考古学〔田中広明〕
9.1.3 地形・地質調査からわかる地震〔宍倉正展〕
a.オン・フォールト古地震調査
b.オフ・フォールト古地震調査
9.2 歴史地震の調査〔西山昭仁〕
9.2.1 史料の種類と特徴
a.史料分類
b.史料批判
c.地震記述の事例と特徴
9.2.2 史料の調査と収集
a.所蔵機関・保存形態
b.調査方法
c.解読作業
9.2.3 史料の整理と刊行
9.2.4 史料記述の分析
a.被害に基づく震度推定
b.建造物の特性と被害との関係
9.2.5 震度分布図の作成
9.2.6 地震史料のデータベース化〔西山昭仁・佐竹健治〕
a.日本の地震史料データベース化の取組み
コラム:世界の歴史地震─ 1755 年リスボン地震の被害と影響─〔西山昭仁〕
9.3 地震考古学の調査〔田中広明〕
9.3.1 地震痕跡の調査─噴砂や側方流動などの事例,発生要因─
a.弘仁地震の地震痕跡
b.発生要因
9.3.2 分析方法─遺構の地震被害と震度の推定─
a.震度の推定
b.遺構の地震被害
9.4 地形・地質学的手法による調査
9.4.1 沈み込み帯の巨大地震の調査〔宍倉正展〕
a.隆起と沈降の痕跡調査
b.津波堆積物調査
c.タービダイトの調査
9.4.2 内陸地震の調査〔近藤久雄〕
a.活断層・震源断層の位置に関する調査
b.発生時期の調査
c.規模の調査
9.5 古地震の地震学的評価〔佐竹健治〕
9.5.1 震度の推定
9.5.2 震源の推定
9.5.3 地震規模の推定
9.5.4 地震の発生時期と長期確率の推定
10.巨大災害をもたらした地震,もたらす可能性のある地震〔佐竹健治〕
10.1 日本海溝・千島海溝の地震〔佐竹健治〕
10.1.1 東北地方太平洋沖地震
10.1.2 日本海溝で過去に発生した地震・津波と長期評価
a.超巨大地震(東北地方太平洋沖型)
b.青森県東方沖〜岩手県沖北部
c.岩手県沖南部
d.宮城県沖
e.福島県沖
f.茨城県沖
g.海溝寄りのプレート間地震(津波地震等)
h.沈み込んだプレート内の地震(青森県東方沖および岩手県沖北部〜茨城県沖)
i.海溝軸外側の地震
10.1.3 千島海溝で過去に発生した地震・津波と長期評価
a.19 世紀以降の地震
b.津波堆積物に基づく先史時代の超巨大地震
10.2 南海トラフの地震〔古村孝志〕
10.2.1 過去の地震
a.1944 年昭和東南海地震,1946 年昭和南海地震
b.1854 年安政東海地震・安政南海地震
c.1707 年宝永地震
d.それ以外の歴史地震
e.津波堆積物などに記載された地震
10.2.2 将来の大地震の予測
a.最大クラスの想定
b.内閣府による最大クラスの地震動・津波
c.地震調査委員会による長期評価・発生確率
コラム:南海トラフの地震による被害想定〔佐竹健治〕
10.3 相模トラフの地震(関東地震)〔佐竹健治〕
10.3.1 過去の関東地震
a.1923年大正関東地震
b.1703年元禄関東地震
c.1495年明応地震
d.1433年永享地震
e.1293年正応地震
f.878年元慶地震
10.3.2 内閣府・地震本部の想定と評価
a.地 震 調 査 委 員 会 に よ る 長 期 評 価
b.国・都によるハザードと被害想定
10.4 内陸・活断層の地震
10.4.1 2024 年能登半島地震 〔平田直〕
a.2020 年から続いた群発地震
b.2024 年 1 月 1 日の大地震
c.地震発生の背景
d.2024 年 1 月の地震の被害
10.4.2 1995 年兵庫県南部地震
a.強震動 〔三宅弘恵〕
b.活断層(野島断層)〔石山達也〕
c.断層モデル 〔三宅弘恵〕
10.4.3 1891 年濃尾地震〔岡田篤正〕
10.5 首都直下の地震〔平田直〕
10.5.1 首都圏直下地震とは何か?
10.5.2 南関東の地震
10.5.3 首都圏への人口集中
10.5.4 これまでに発生した首都圏の大地震
コラム:確率を計算するのに用いた統計モデル─ポアソンモデルと BPT モデル
10.5.5 首都直下地震の被害想定
10.6 世界の大地震〔佐竹健治〕
10.6.1 北太平洋周辺の地震
10.6.2 中南米の地震
10.6.3 インド洋の地震
10.6.4 インド・中国周辺の地震
10.6.5 ヨーロッパの地震
11.地震活動・災害誘因(ハザード)の予測〔平田直〕
11.1 地震発生の予測
11.1.1 地震発生の長期予測 〔佐竹健治〕
a.地震調査研究推進本部の長期評価
b.海溝型地震の長期予測
c.主要活断層で起こる地震の長期評価
d.地域評価
e.海域活断層の長期評価
11.1.2 地震予測とその検証 〔鶴岡弘〕
11.1.3 プレート境界のモニタリングと地震発生予測〔土井恵治〕
11.1.4 地球電磁気学的手法による地震予知研究〔鴨川仁〕
11.1.5 地球化学的・水文学的手法による地震予知研究〔小泉尚嗣〕
11.1.6 民間の地震予知・予測情報サービス〔小泉尚嗣・鴨川仁〕
11.2 地震動の予測〔藤原広行〕
11.2.1 確率論的地震動予測
11.2.2 震源断層を特定した地震動予測
11.2.3 長周期地震動の予測
11.2.4 津波の予測〔土肥裕史・藤原広行〕
11.3 災害誘因(ハザード)の即時予測
11.3.1 緊急地震速報〔束田進也・林元直樹〕
11.3.2 津 波 警 報〔長谷川洋平〕
a.リアルタイム防災情報としての津波警報
b.東日本大震災の大津波による見直し
c.火山噴火による津波への対応
d.今後の津波警報の展望
11.3.3 余 震 予 測〔土井恵治〕
11.3.4 伊豆東部の地震活動の予測〔森田裕一〕
11.3.5 新しい地震動即時予測〔干場充之〕
11.4 地震予知研究と災害の軽減に貢献する地震火山観測研究計画〔平田直〕
11.4.1 ブループリント以前
11.4.2 第 1 次から第 7 次地震予知計画
a.第 1 次から第 3 次までの地震予知計画
b.第 4 次から第 7 次までの地震予知計画
11.4.3 地震予知のための新たな観測研究計画
11.4.4 災害の軽減に貢献する地震火山観測研究計画
11.5 地震防災のための地震関連組織
11.5.1 地震調査研究推進本部〔平田直〕
11.5.2 内閣府・中央防災会議〔横田崇〕
a.内閣府における防災業務
b.中央防災会議
c.専門調査会
d.緊急参集チームと特定災害対策本部,非常災害対策本部および緊急災害対策本部
e.都道府県および市町村における防災体制
11.5.3 地震防災対策強化地域判定会〔土井恵治〕
コラム:東海地震の予知体制
11.5.4 科学技術・学術審議会測地学分科会〔平田直〕
11.5.5 地震予知連絡会〔今給黎哲郎〕
11.5.6 地震研究所〔平田直〕
付録資料 1:1900 年以降の地震カタログの表〔室谷智子〕
資料 2:日本の主な地震の表〔茅野一郎・宇津徳治・西山昭仁〕
資料 3:海外の主な地震の表(16 世紀以降)〔宇津徳治・西山昭仁〕
索引
事項索引
地震索引