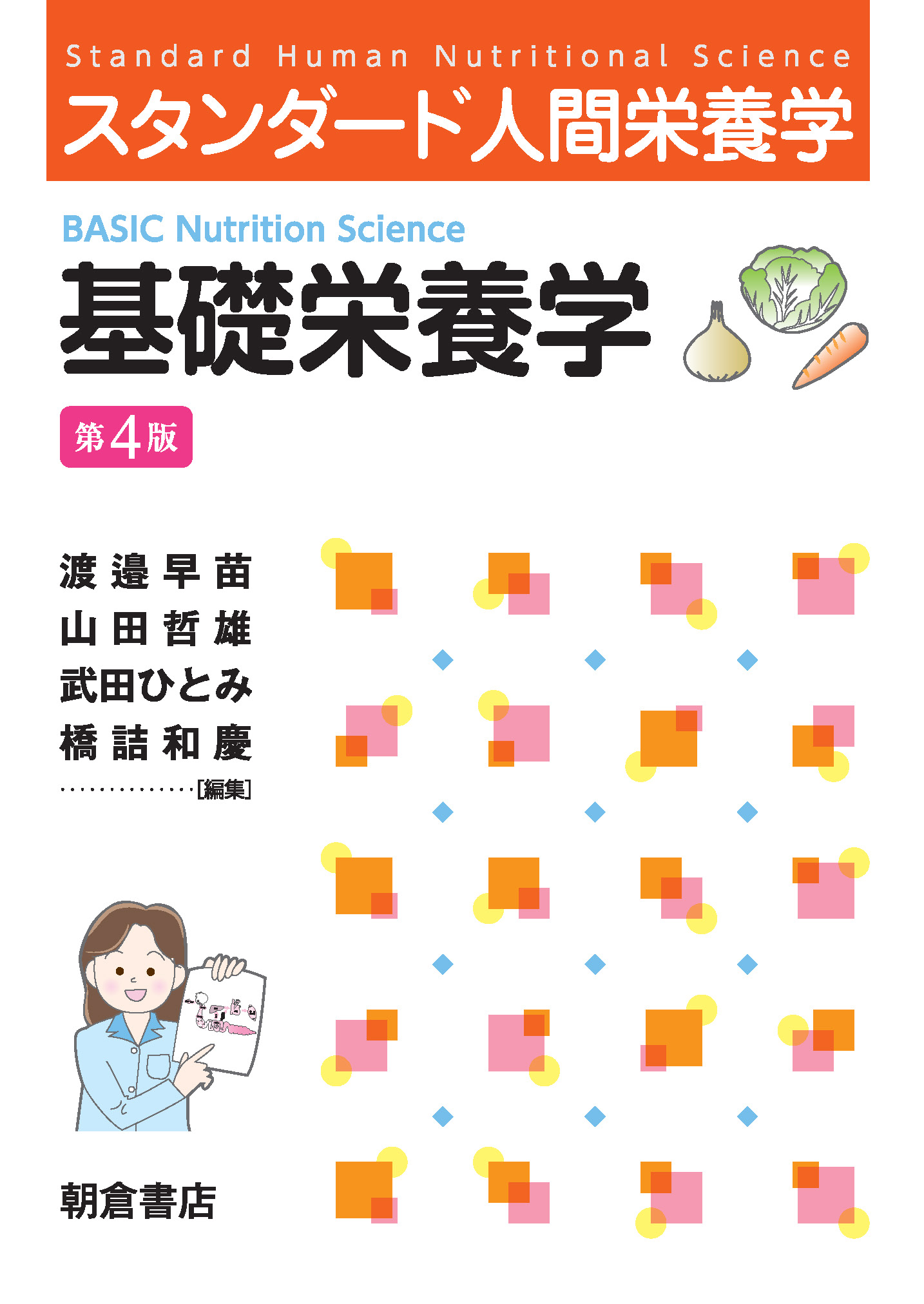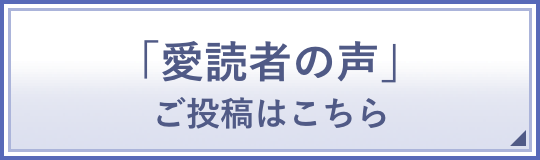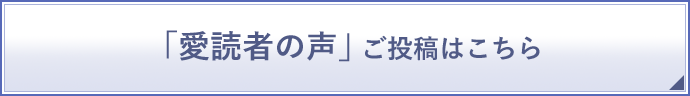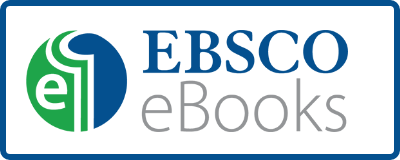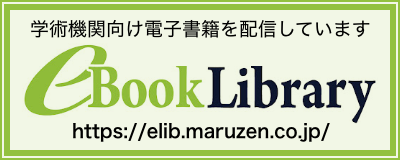BOOK SEARCH
内容紹介
豊富な図表とともにわかりやすく解説する教科書。管理栄養士国家試験出題基準ガイドライン準拠。2色刷。〔内容〕栄養の概念/食物の摂取/栄養素の消化吸収と体内動態/エネルギー代謝/炭水化物の栄養/脂質の栄養/たんぱく質の栄養/ビタミンの栄養/ミネラルの栄養/水と電解質の栄養/栄養素の発見と推進。
編集部から
目次
第Ⅰ部 人間栄養学
第 1 章 栄養の概念
1.1 栄養の定義
1)栄養
2)栄養素
1.2 栄養と健康・疾患
1)栄養学の歴史
2)欠乏症・過剰症
3)生活習慣病
4)健康増進
1.3遺伝形質と栄養の相互作用
1)栄養素に対する応答の個人差
2)生活習慣病と遺伝子多型
3)倹約(節約)遺伝子仮説
第 2 章 食物の摂取
2.1 空腹感・満腹感と食欲
1)空腹感・満腹感
2)摂食量の調節
2.2 食事のリズムとタイミング
1)日内リズムと栄養補給
第 3 章 栄養素の消化・吸収と体内動態
3.1 消化・吸収と栄養
1)水溶性栄養素
2)疎水性栄養素
3.2 消化の過程
1)口腔内消化
2)胃内消化
3)小腸内消化
4)膜消化
3.3 管腔内消化の調節
1)脳相・胃相・腸相
2)自律神経系による調節
3)消化管ホルモンによる調節
3.4 吸収の過程
1)膜の透過
2)受動輸送・能動輸送・膜動輸送
3.5 栄養素の吸収
1)炭水化物
2)脂質
3)たんぱく質
4)ビタミン
5)ミネラル
6)水
3.6 栄養素の体内動態
1)門脈系
2)リンパ系
3.7 生物学的利用度
1)消化吸収率
2)栄養価
3.8 栄養素の排泄
1)水溶性栄養素
2)疎水性栄養素
第 4 章 エネルギー代謝
4.1 エネルギー代謝の概念
1)基礎代謝
2)安静時代謝
3)睡眠時代謝
4)活動代謝
5)メッツ(METs),身体活動レベル(PAL)
6)食事誘発性熱産生(DIT)
4.2 エネルギー代謝の測定法
1)直接法,間接法
2)呼気ガス分析
3)呼吸商,非たんぱく質呼吸商
4)二重標識水法
4.3 生体利用エネルギー
1)物理的燃焼値,生理的燃焼値
2)臓器別エネルギー代謝
第Ⅱ部 栄養素の代謝と役割
第 5 章 炭水化物の栄養
5.1 糖質の体内代謝
1)糖質の栄養学的特徴
2)糖質の体内代謝
3)食後・食間期の糖代謝
4)糖質代謝の臓器差と臓器間連携
5.2 血糖とその調節
1)インスリンの作用
2)血糖曲線
3)肝臓の役割
4)筋肉・脂肪組織の役割
5)コリ回路,グルコース -アラニン回路
5.3 他の栄養素との関係
1)相互変換
2)ビタミン B1必要量の増加
3)たんぱく質節約作用
5.4 食物繊維・難消化性炭水化物
1)不溶性食物繊維・水溶性食物繊維
2)難消化性でんぷん・難消化性炭水化物
3)腸内細菌叢と短鎖脂肪酸
第 6 章 脂質の栄養
6.1 脂質の体内代謝
1)脂質の栄養学的特徴
2)食後・食間期の脂質代謝
3)脂質代謝の臓器差
6.2 脂質の臓器間輸送
1)リポたんぱく質
2)遊離脂肪酸
3)ケトン体
6.3 コレステロール代謝の調節
1)コレステロールの合成,輸送,蓄積
2)フィードバック調節
3)コレステロール由来の体成分
4)胆汁酸の腸肝循環
6.4 摂取する脂質の量と質の評価
1)脂肪エネルギー比率
2)飽和脂肪酸,一価不飽和脂肪酸,多価不飽和脂肪酸
3)n-6系脂肪酸,n-3系脂肪酸
4)必須脂肪酸
5)脂肪酸由来の生理活性物質
6.5 他の栄養素との関係
1)ビタミン B1節約作用
2)エネルギー源としての糖質の節約
第 7 章 たんぱく質の栄養
7.1 たんぱく質・アミノ酸の体内代謝
1)たんぱく質・アミノ酸の栄養学的特徴
2)食後・食間期のたんぱく質・アミノ酸代謝
3)たんぱく質・アミノ酸の臓器差
4)分岐鎖アミノ酸
5)栄養アセスメントたんぱく質
7.2 摂取するたんぱく質の量と質の評価
1)不可欠アミノ酸
2)アミノ酸価
3)アミノ酸の補足効果
4)たんぱく質効率
5)窒素出納・生物価
7.3 他の栄養素との関係
1)エネルギー代謝とたんぱく質
2)糖新生とたんぱく質代謝
第 8 章 ビタミンの栄養
8.1 ビタミンの分類
1)脂溶性ビタミン
2)水溶性ビタミン
8.2 ビタミンの栄養学的特徴と機能
1)補酵素とビタミン
2)抗酸化作用とビタミン
3)ホルモン様作用とビタミン
4)血液凝固とビタミン
5)エネルギー代謝とビタミン
6)糖質・脂質・アミノ酸の代謝とビタミン
7)核酸代謝とビタミン
8)一炭素単位代謝とビタミン
9)カルシウム代謝とビタミン
8.3 ビタミンの吸収と体内利用
1)脂溶性ビタミンと脂質の消化吸収の共通性
2)水溶性ビタミンの組織飽和と尿中排泄
3)腸内細菌叢とビタミン
4)ビタミン B12吸収機構の特殊性
第 9 章 ミネラルの栄養
9.1 ミネラルの分類
1)多量ミネラル
2)微量ミネラル
9.2 ミネラルの栄養学的特徴と機能
1)硬組織とミネラル
2)神経・筋肉の機能維持とミネラル
3)血圧調節とミネラル
4)糖代謝とミネラル
5)酵素とミネラル
9.3 ミネラルの吸収と体内利用
1)カルシウムの吸収と体内利用
2)鉄の吸収と体内利用
第 10 章 水と電解質の栄養
10.1 水の分布と栄養学的特徴
10.2 水の出納
1)代謝水
2)不可避尿
3)不感蒸泄
4)水分必要量
5)脱水・浮腫
10.3 電解質代謝と栄養
1)水・電解質・酸塩基平衡の調節
2)高血圧とナトリウム・カリウム
第 11 章 栄養素の発見と推進
11.1 呼吸とエネルギー代謝
11.2 三大栄養素の発見
1)脂肪
2)炭水化物
3)たんぱく質
11.3 ビタミンの発見
11.4 ミネラル(無機質)の発見
11.5 日本の栄養学の夜明け
11.6 これからの栄養学
1)栄養学の実践
2)社会の変化と人々の生活
3)少子高齢化の進展と疾病構造の変化
4)政策・制度の変遷と栄養士・管理栄養士の養成
5)栄養学と SDGs(エスディージーズ)
6)栄養学のレガシーを未来へ
参考図書
過去問題
第 38 回
第 37 回
第 36 回
付表
付表 1 身体活動・運動の推奨事項一覧
付表 2 健康づくりのための休養指針
付表 3 睡眠に関する推奨事項
索 引