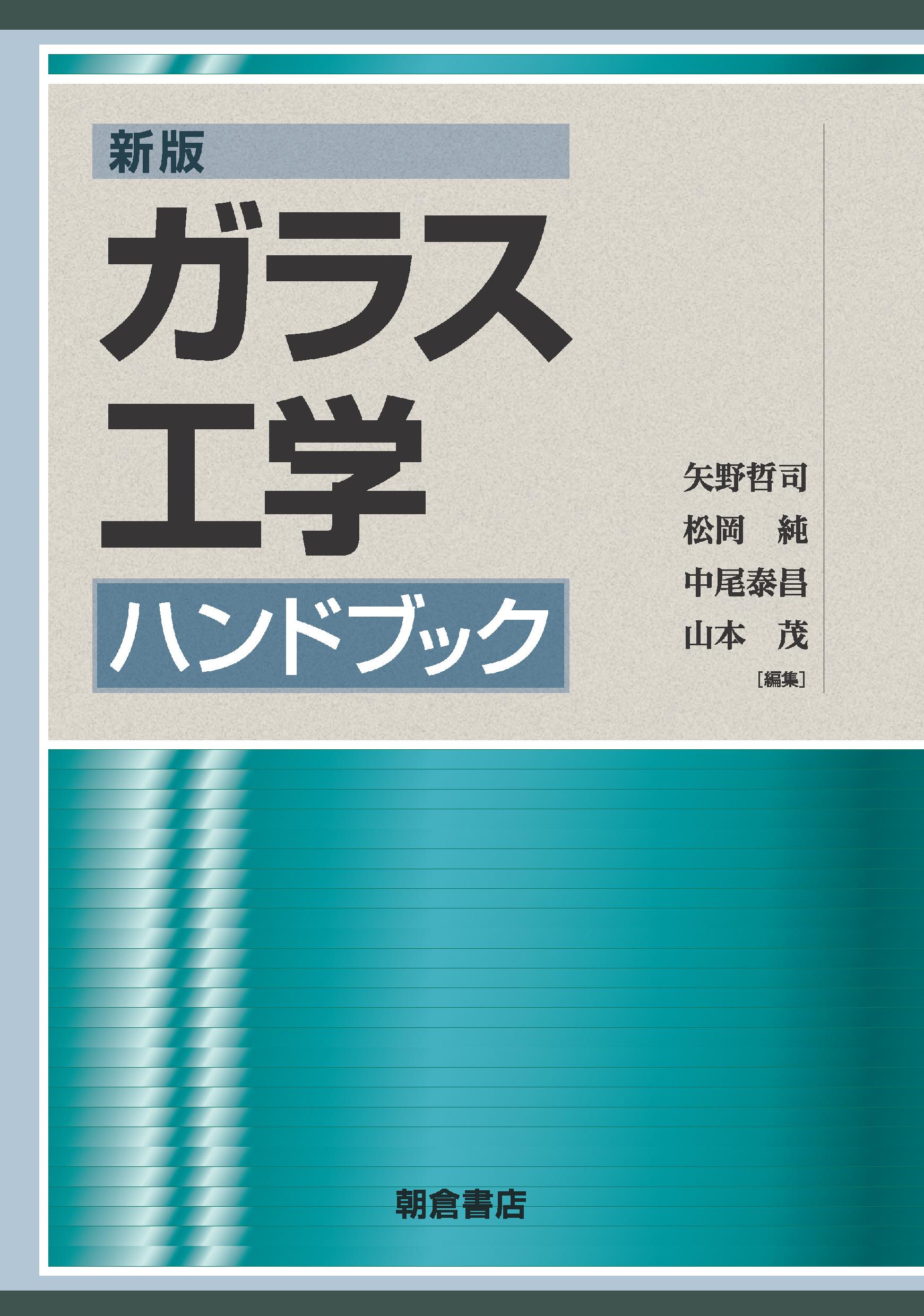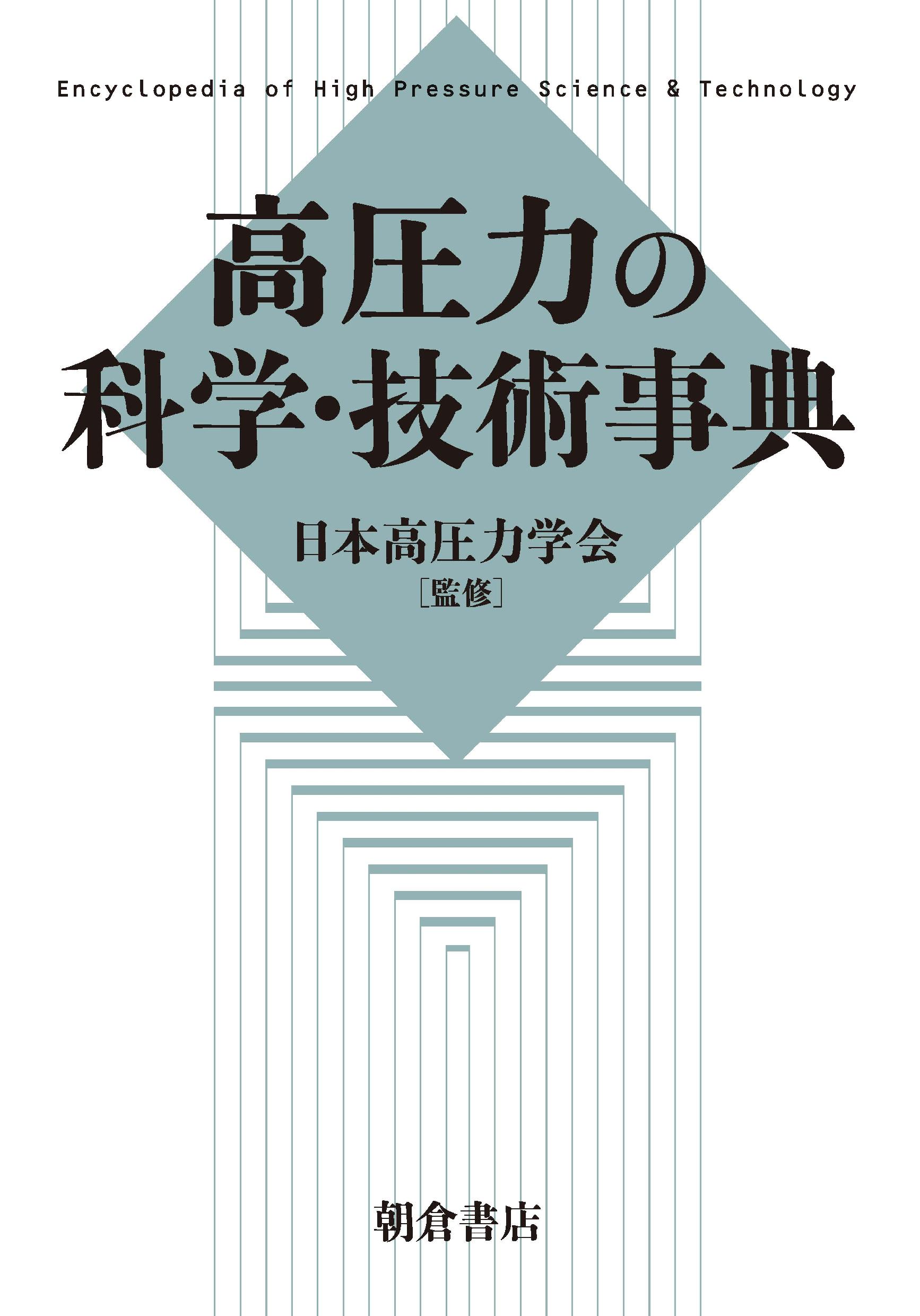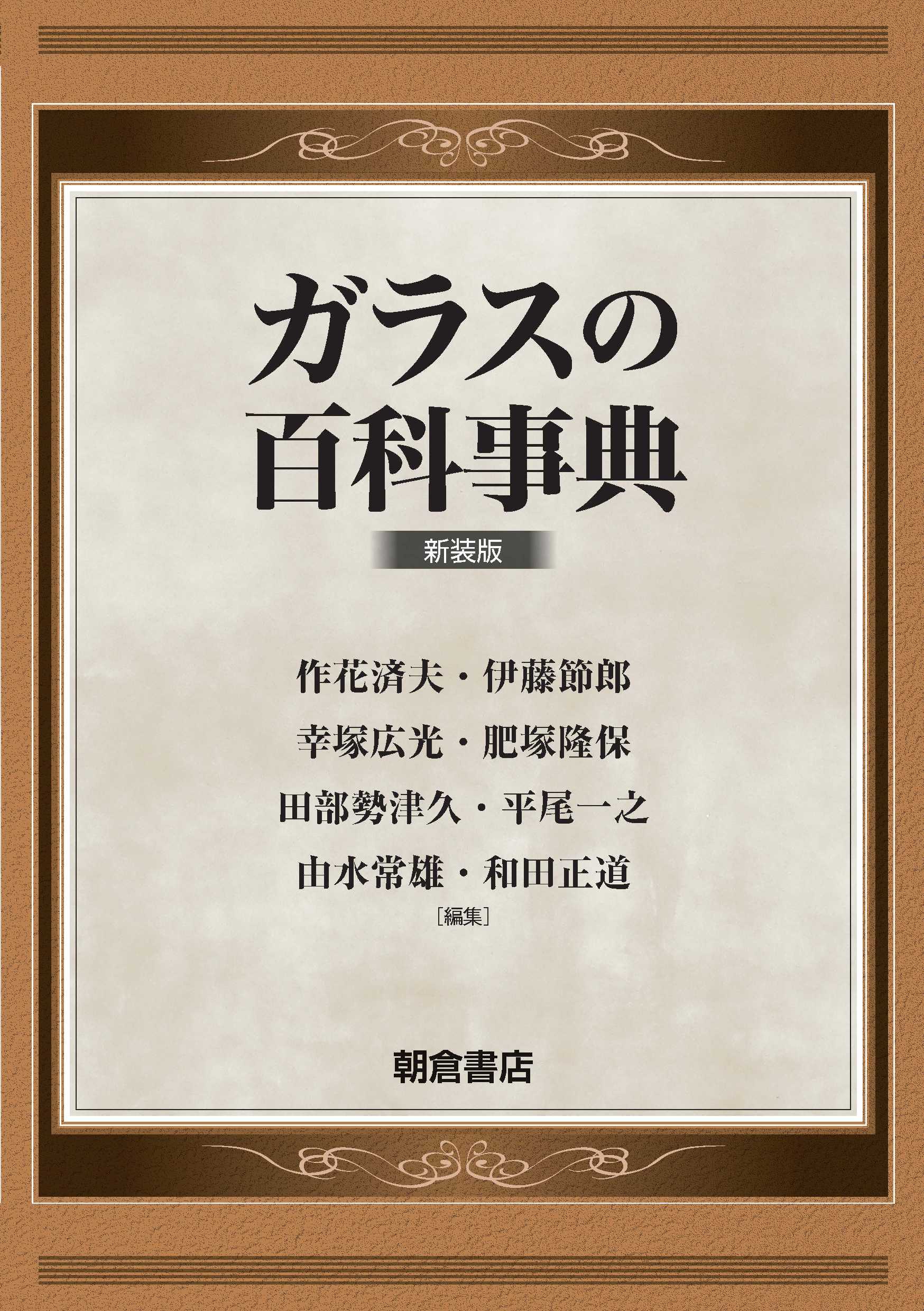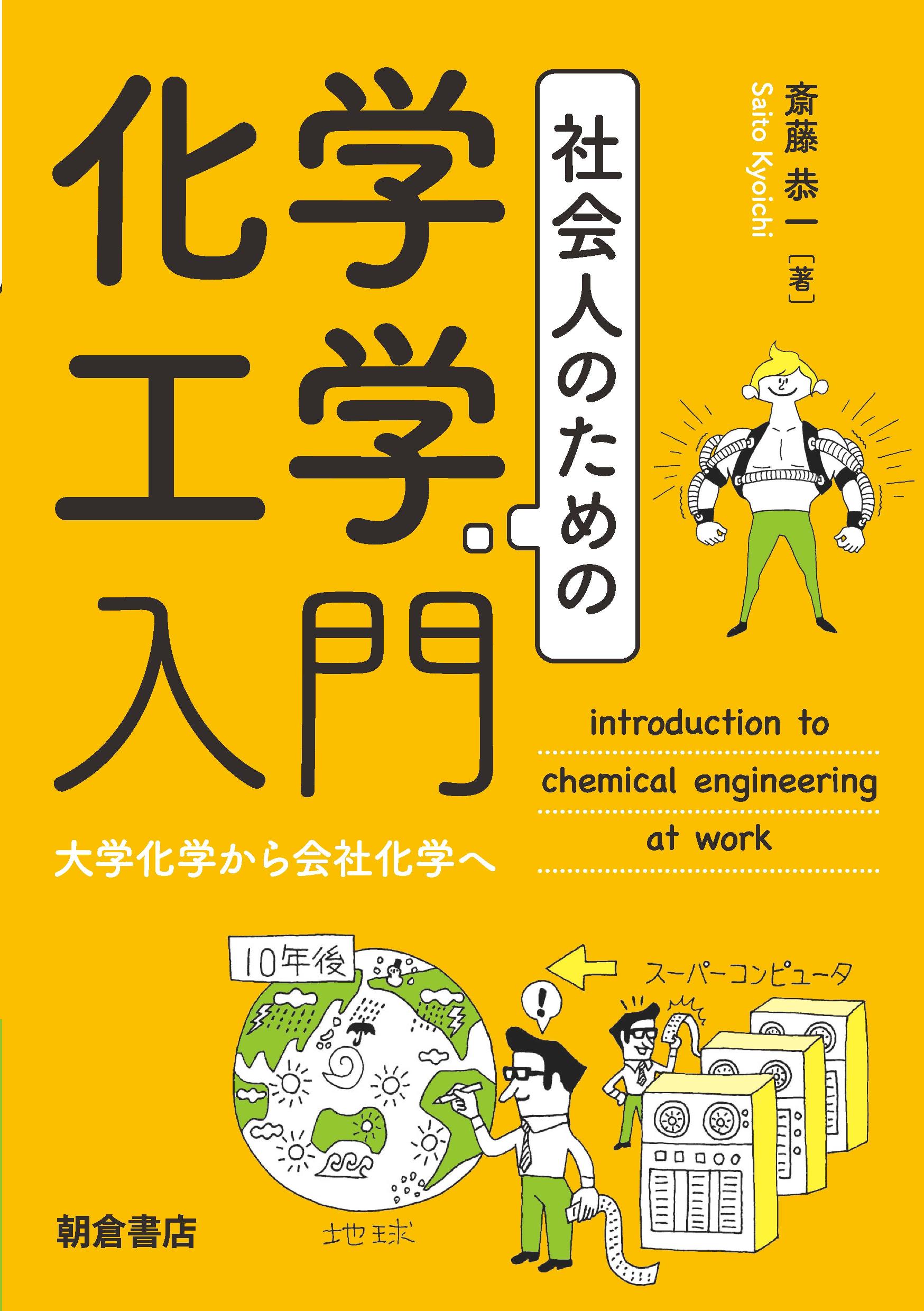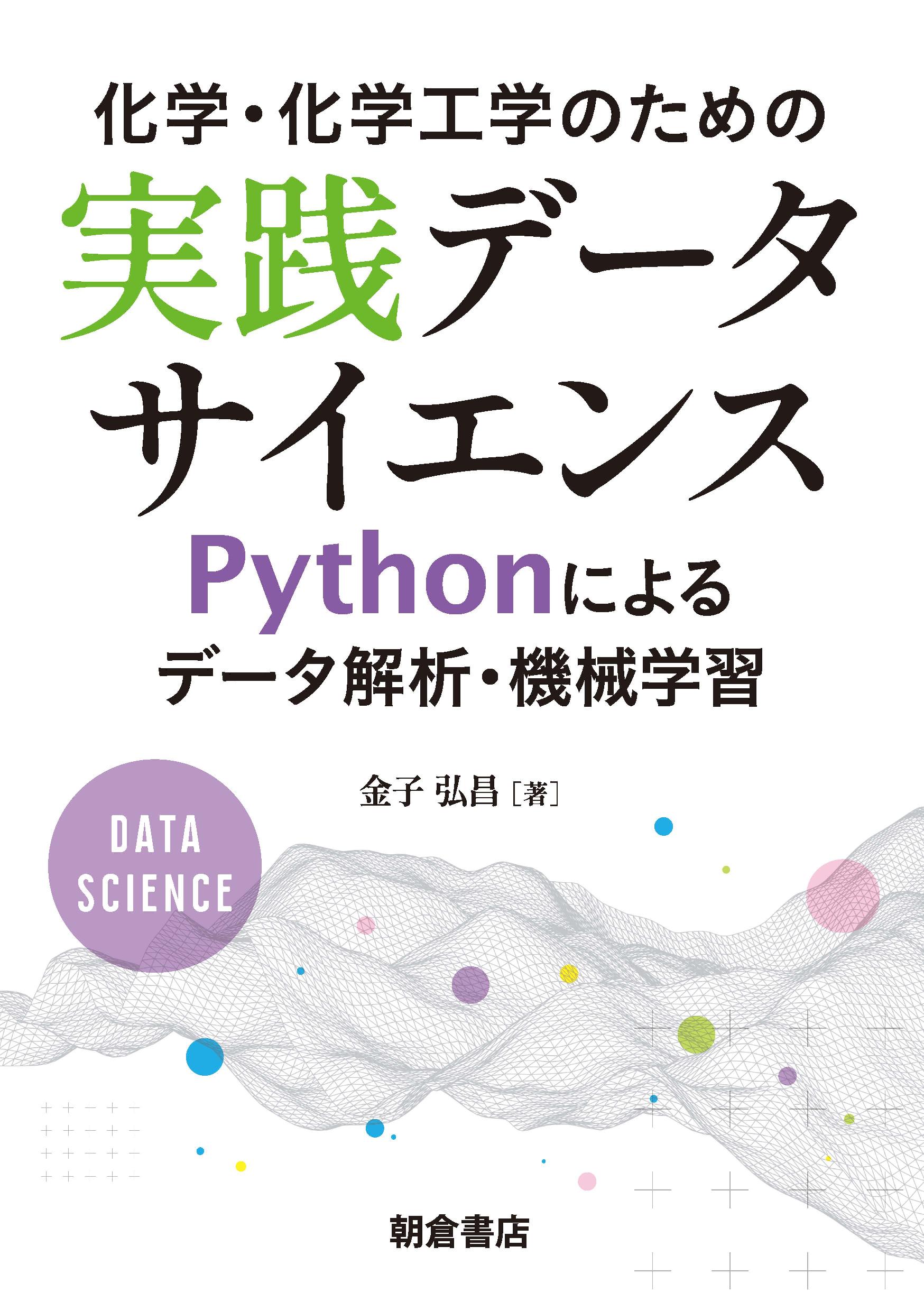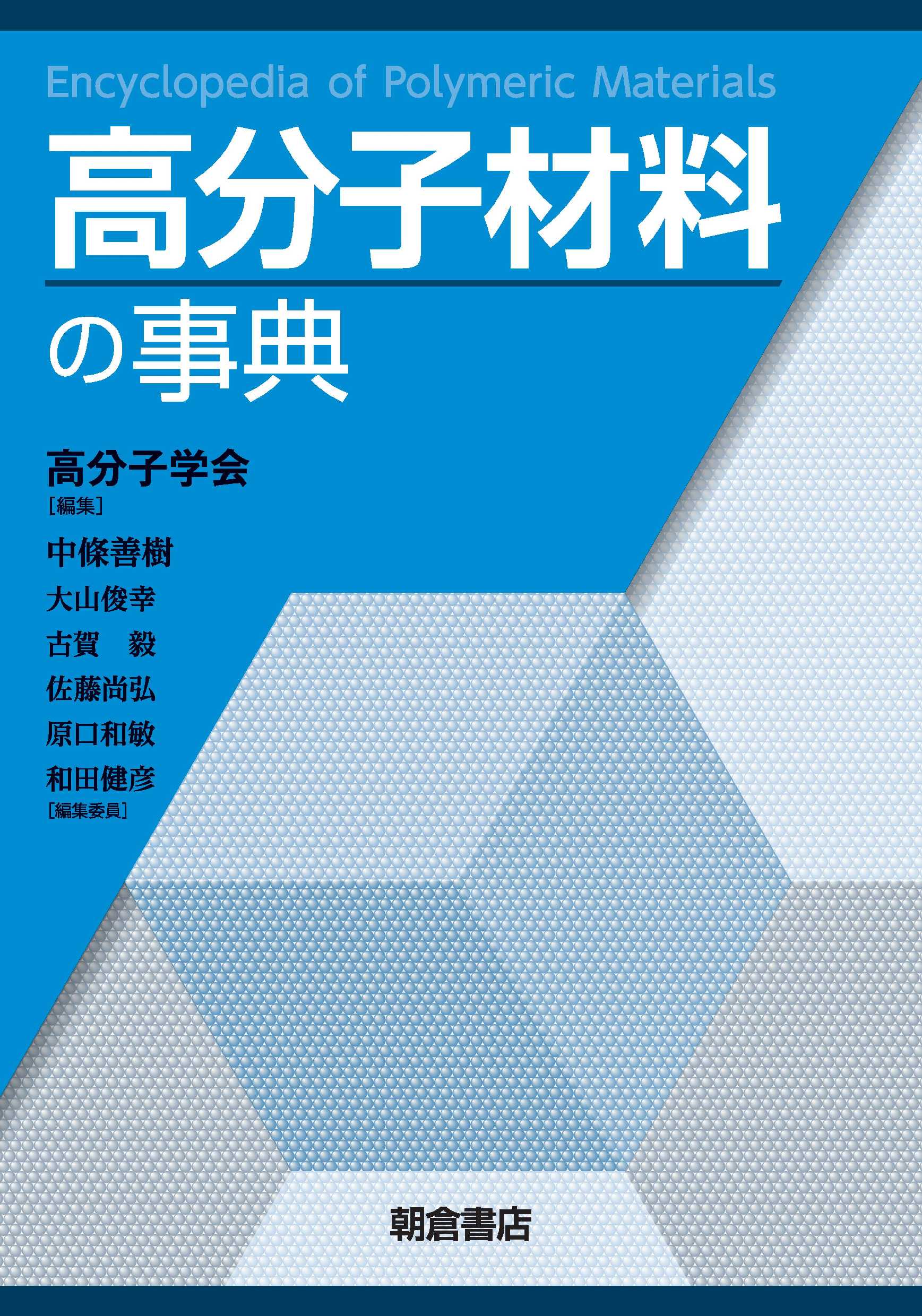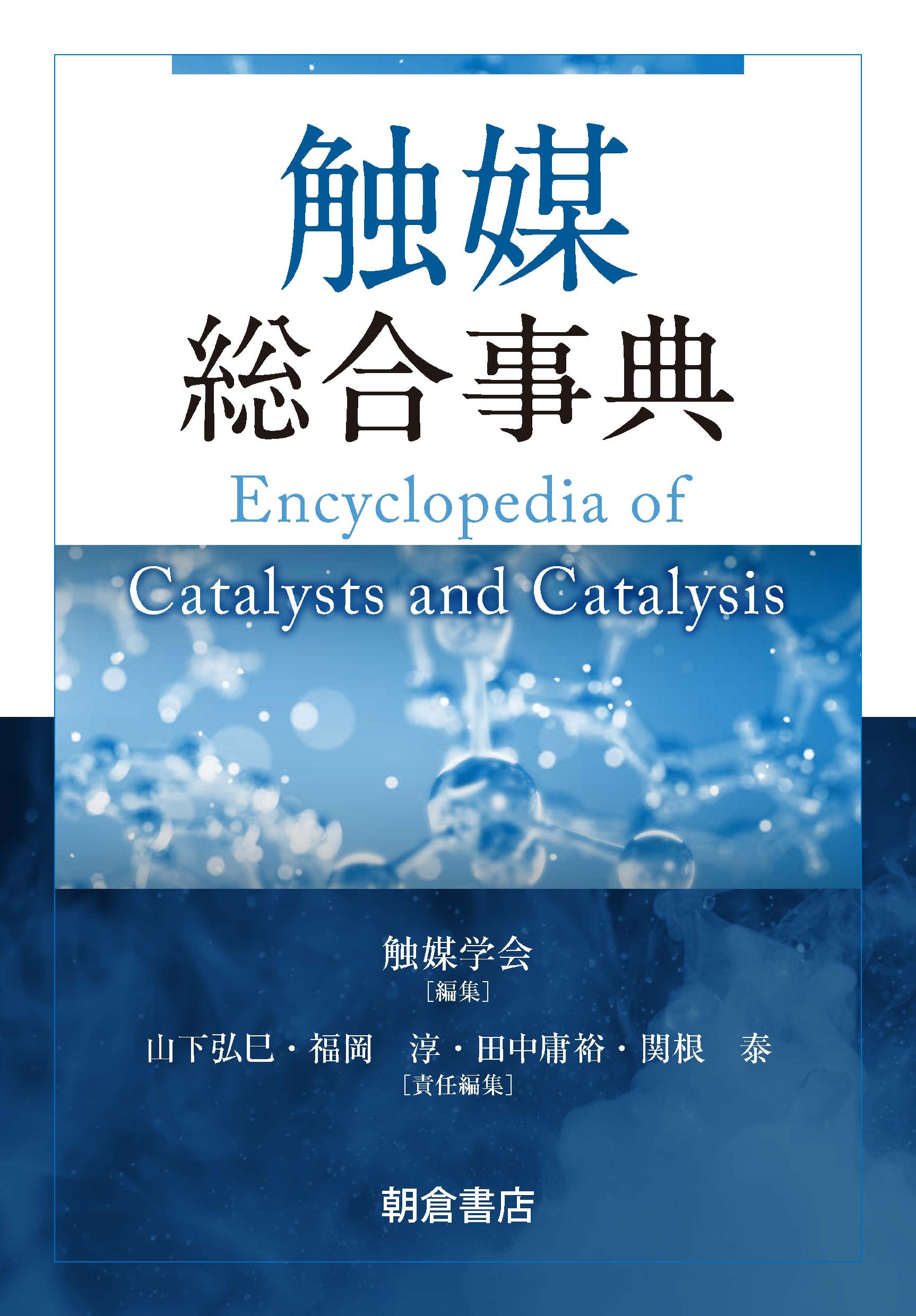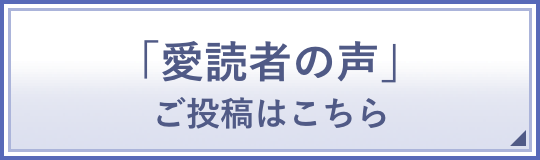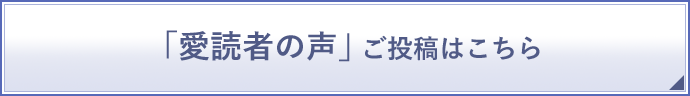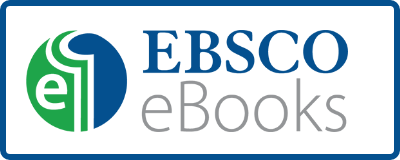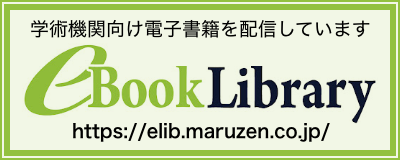BOOK SEARCH
内容紹介
ガラスの科学・工学の理論から応用まで網羅して詳細に解説した,定評あるハンドブックの改訂新版.研究・解析法の発展や環境・持続性社会を見据えた技術革新などもカバー.〔内容〕ガラスとは/構造/性質/ガラス融液の性質/ガラスと水/物性・構造シミュレーション/ガラス溶融の科学/製造/加工・表面処理/製品/ガラスと環境
編集部から
序
紀元前より用いられてきたガラスは,これまでの数千年にもわたる長い歴史の中で人々の生活様式をはじめ,科学・技術の萌芽と発展に対して数々の革新的な役割を果たしてきました.それは,ガラス材料が持つ物理的・化学的特徴とその多様性に起源があり,人類がそれらを理解・制御するための知識と技術を集積・発展させ,いくつもの果実として結実させてきたからであり,究極的ともいえる高い性能を実現させてきています.迎えた21世紀の現在においても,その重要性は一層増しています.私たちの生活の細部にわたってガラス材料は浸透しています.例えば現在社会の根幹をなす情報システムは,ガラスを抜きには成立せず,多様な製品と機能をもったガラスが使用され,新たな発展も求められています.
本書は,森谷ほか編『ガラス工学ハンドブック』(1963年),作花ほか編『ガラスハンドブック』(1975年),山根ほか編『ガラス工学ハンドブック』(1999年)の新版として企画されました.ガラスの工業生産は19世紀後半から一段と加速し,他の産業と並行して人々の生活を変えてきました.1963年版「ガラス工学ハンドブック」が出版された頃,日本は戦後の復興から脱して高度成長期の入り口にありました.1975年版の出版の頃には先進国の仲間入りを果たし,大量消費社会へ向けた製造業の成長真只中にありました.ガラスの製造は,板ガラスにおいてはフロート法の展開と大型化へ加速された時期でもありました.飛躍的に優れた平坦性を持つ板ガラスの登場は人々を驚かせたことでしょう.1999年版が出版されたときには,ディスプレィはまだブラウン管CRTが中心で,平面ディスプレィが登場し始め,日本では種々の原理の表示素子の開発が行われていました.日本の高精度・高精細なものづくり技術が世界を席巻していた時代の始まりでもあり,ガラスの可能性に胸を躍らせていた頃でした.
21世紀に入ってからの四半世紀,さまざまなアクシデントにより大きく社会が変化しました.その変化の波は,IT技術,グローバリゼーション,地球環境の変化などのいくつもの要素によっても大きく変動し,地球規模で変わる時代となっています.エネルギーに関する課題は,化石燃料多消費産業の一つでもあるガラスの製造にも大きく影響を与えはじめています.優れたガラス製品を供給することと,地球環境負荷を低減することの異なる方向性の中でどのように答えられるのか,1999年版当時にはない大きなトピックスとなっています.
本書を編集するにあたって,1999年版以降に積み上げられた新しい学術,技術の知見を組み入れるだけでなく,デジタル・AIといった情報革命とガラス,環境とガラス,に関する進捗を組み入れました.ガラスの構造と物性は,評価方法・解析方法の進化によって新たな展開が見出されており,計算機をツールとしたマテリアルズインフォマティクスの活用の時代が到来しています.融液物性,溶融技術も新たな製品の登場により一層の理解と開発が望まれ,進化しています.特にエネルギー有効利用,CO2排出抑制の観点から,溶融炉の加熱技術にも大きな変化が生じています.以上のような観点から,ガラスおよび構造を第I~III編にて,ガラス融液の性質を第IV編にて,ガラスに大きな影響を及ぼす水の影響を第V編にてまとめ,さらにガラス科学における物性・構造に関する計算機利用をまとめた第VI編,ガラス製造の観点から融液・プロセスをまとめた第VII~IX編,ガラス製品の最前線をまとめたX編,そしてガラスと環境をまとめたXI編からなる構成にしました.
今後,社会におけるガラスの利用はさらに重要となり,新たな材料・技術開発が求められることは間違いないでしょう.1999年版から四半世紀,本書が新たな時代に向けて,ガラスの科学・工学に携わる研究者,技術者,学生,さらにガラス材料のユーザーの皆様に広く活用され,ガラスの科学・工学の一層の発展に助する役割を果たしてくれることを,編集委員一同強く願うところです.
本書を出版するにあたり,執筆の労をとっていただきました第一線の研究者,技術者の皆様には,厚くお礼申し上げるとともに,査読にご協力いただきました皆様にも感謝申し上げます.
2025年5月
編集代表 矢野哲司
目次
■第I編 ガラスとは
1 ガラス状態 [井上博之]
1.1 ガラスとは何か
1.2 ガラス転移
1.3 ガラスの作製方法
1.3.1 気相合成法
1.3.2 液相法
2 ガラスの種類と用途 [山崎博樹]
2.1 ガラスの機能とその応用(概論)
2.2 主なガラス系とその用途
2.2.1 ソーダ石灰ガラス
2.2.2 ホウケイ酸ガラス
2.2.3 アルミノケイ酸ガラス
2.2.4 シリカガラス
2.2.5 鉛ガラスとその代替ガラス
2.2.6 ホウ酸塩ガラス
2.2.7 リン酸塩ガラス
2.2.8 フッ化物ガラス
2.2.9 カルコゲナイドガラス
2.2.10 結晶化ガラス
2.2.11 他の特殊組成ガラス
■第II編 ガラスの構造
1 ガラスの構造論
1.1 ガラス形成の理論 [山田明寛]
1.1.1 Zachariasen則
1.1.2 結合の強さ
1.1.3 網目構造の制約
1.1.4 冷却速度と粘度
1.2 ガラスの構造 [森 龍也,山田明寛]
1.2.1 短距離構造
1.2.2 中距離構造
1.2.3 自由体積
1.3 ガラス融液の構造 [清水雅弘]
1.3.1 多成分ケイ酸塩系ガラスとSiO2ガラス
1.3.2 Na2O-GeO2融液とGeO2融液の構造
1.3.3 Na2O-B2O3融液
1.3.4 網目修飾イオンの配位状態の温度依存性
1.4 ガラスの酸・塩基 [菅原 透]
1.4.1 ガラスの光学的塩基度
1.4.2 ガラスの構造,特性と塩基度
1.5 ガラスの緩和 [北村直之]
1.5.1 ガラスの緩和現象とガラス転移理論の変遷
1.5.2 ガラス転移点近傍での緩和現象
2 ガラスの構造解析
2.1 X線および中性子回折法 [小野寺陽平]
2.2 X線吸収分光法(XAFS) [山田明寛]
2.2.1 X線吸収端近傍微細構造(XANES)
2.2.2 広域X線吸微細構造(EXAFS)
2.2.3 軟X線XAFS
2.2.4 先端的な測定
2.3 核磁気共鳴分析法 [大窪貴洋]
2.3.1 NMRの原理
2.3.2 NMR測定
2.3.3 ガラスのNMR測定
2.3.4 発展的なNMR解析
2.4 振動スペクトル法 [森 龍也,山田明寛]
2.4.1 赤外吸収分光法
2.4.2 ラマン散乱分光法
2.4.3 構造情報
2.5 X線光電子分光法 [紅野安彦]
2.6 その他の解析法
2.6.1 メスバウアー分光法
2.6.2 電子スピン共鳴分光法
2.6.3 紫外可視分光法
2.6.4 陽電子消滅寿命計測法
2.6.5 透過型電子顕微鏡および電子線回折法
3 ガラス化範囲 [篠崎健二,高橋儀宏]
3.1 ガラス形成の速度論
3.2 網目形成成分を含む酸化物のガラス化範囲
3.2.1 ガラス形成能の一般的法則
3.2.2 酸化物のガラス化範囲
3.3 網目形成成分を含まない酸化物のガラス化範囲
3.4 カルコゲナイドのガラス化範囲
3.5 その他の非酸化物のガラス化範囲
3.5.1 フッ化物およびハロゲン化物ガラス
3.5.2 独立アニオンガラス
■第III編 ガラスの性質
1 力学的性質
1.1 密 度 [上田 基]
1.1.1 密度の定義
1.1.2 密度の測定法
1.1.3 組成と密度の関係
1.1.4 熱処理による密度変化
1.1.5 密度へのその他の影響因子
1.2 弾 性 [稲葉誠二]
1.2.1 弾性率の定義
1.2.2 固体に共通する弾性率の支配因子
1.2.3 弾性率測定方法
1.2.4 弾性率の組成依存性
1.2.5 高弾性率ガラスの組成・構造的特徴
1.2.6 ポアソン比とガラス構造の関連
1.2.7 弾性率の温度依存性と圧力依存性
1.2.8 擬弾性と内部摩擦
1.2.9 ガラス転移温度付近での粘弾性挙動
1.3 硬 度 [加藤嘉成]
1.3.1 硬度の測定方法
1.3.2 圧子周辺の構造変化
1.3.3 硬度とガラス組成
1.3.4 クラックの入りにくさ,脆さ
1.4 強 度 [吉田 智,小池章夫]
1.4.1 理論強度
1.4.2 実用強度
1.4.3 ガラスの強度の評価
1.4.4 実用強度に及ぼす各種の要因
1.4.5 統計的評価手法
1.4.6 ガラス組成と強度の関係
1.4.7 強度の工業的取扱い
1.5 ガラスの破面解析 [宮宅ゆみ子]
1.5.1 ガラスの破面
1.5.2 熱割れと曲げ応力割れ
1.5.3 強化ガラスの割れ
2 熱的性質
2.1 熱容量および比熱 [紅野安彦]
2.1.1 固体の熱容量
2.1.2 比熱の測定法
2.1.3 固体の低温比熱
2.1.4 ガラスの低温比熱の組成依存性
2.1.5 ガラス転移温度付近での比熱挙動
2.2 熱伝導
[助永壮平,西 剛史,太田弘道,柴田浩幸]
2.2.1 熱伝導率と熱拡散率
2.2.2 熱伝導率の測定法
2.2.3 ガラスの熱伝導率の温度依存性
2.2.4 室温近傍での熱伝導率の組成依存性
2.3 熱膨張 [山田修史]
2.3.1 測定法
2.3.2 熱膨張のガラス組成依存性
[紅野安彦]
2.4 耐熱性・耐熱衝撃性 [宮宅ゆみ子]
2.4.1 ガラス内の温度差と熱応力
2.4.2 物理強化ガラスの耐熱性
2.4.3 窓ガラスの「熱割れ」
3 光学的性質
3.1 光の透過と吸収・散乱 [斉藤 全]
3.1.1 紫外吸収端
3.1.2 可視吸収
3.1.3 赤外吸収端
3.1.4 不純物による赤外吸収
3.1.5 散 乱
3.2 ガラスの透過率・反射率・散乱
[斎藤 全]
3.2.1 透過率
3.2.2 反射率
3.2.3 散 乱
3.3 着 色 [上田純平]
3.3.1 遷移金属イオンによる着色
3.3.2 希土類イオンによる着色
3.3.3 コロイドによる着色
3.3.4 ガラス母体の吸収
3.3.5 その他の着色
3.4 屈折率と分散 [藤野 茂]
3.4.1 屈折率
3.4.2 屈折率の波長分散性
3.4.3 屈折率の温度依存性
3.4.4 屈折率の測定方法
3.5 発 光 [上田純平]
3.5.1 遷移金属イオンの発光
3.5.2 希土類イオンの発光
3.5.3 典型元素イオンの発光
3.5.4 その他の発光
3.5.5 レーザーガラス
4 電気的性質
4.1 ガラスの絶縁性と伝導性
[林 晃敏,作田 敦,大幸裕介]
4.1.1 アレニウスプロット
4.1.2 絶縁性
4.2 ガラスのイオン伝導性
4.2.1 プロトン伝導性
4.2.2 フッ化物イオン伝導性ガラス
4.2.3 超イオン伝導性ガラス
4.2.4 混合アルカリ効果(MAE)
4.3 ガラスの電子伝導性
4.3.1 ホッピング型伝導
4.3.2 キャリアの種類とゼーベック係数
4.3.3 カルコゲン化物ガラス
4.4 ガラスの誘電特性
4.5 電気的性質の測定
4.6 イオン伝導性ガラス
4.7 電子伝導性カルコゲナイドガラス
[角野広平]
4.8 混合伝導性ガラス
[大幸裕介,作田 敦,林 晃敏]
5 化学的性質
5.1 ガラスの化学的性質の評価 [高石大吾]
5.1.1 耐久性評価法
5.1.2 長期耐水性評価
5.2 ガラス表面の水との化学反応
5.2.1 ガラス表面の構造
5.2.2 ガラス表面の反応機構
5.3 酸・アルカリとの反応
5.3.1 酸との反応
5.3.2 アルカリとの反応
5.4 種々の水溶液との反応
5.5 ガラスの組成と化学的耐久性
5.5.1 組成と化学的耐久性の定量的理解
5.5.2 耐水性
5.5.3 耐酸性
5.5.4 耐アルカリ性
5.5.5 ガラスの構造と化学的耐久性
5.6 水和層の生成
5.7 耐候性
5.8 ガラス表面のキャラクタリゼーション
[山本雄一]
5.8.1 組成分析法
5.8.2 OH分析法
5.8.3 各種物性への水分の影響
6 磁気的性質 [寺門信明]
6.1 ガラスの磁気的性質
6.1.1 反磁性
6.1.2 常磁性
6.2 ガラスの磁気光学的性質
6.3 微結晶析出ガラスの磁気的性質
7 放射線・紫外線に対する性質 [梶原浩一]
7.1 概 要
7.2 X線やγ線による欠陥形成
7.3 紫外線照射による欠陥形成
7.4 粒子線照射による欠陥形成
7.5 不純物の関与する欠陥過程
7.6 照射誘起密度変化,その他の現象
8 ガラスの組成分析 [竹中敦義]
8.1 化学分析法
8.2 蛍光X線法
8.3 表面近傍の組成分析
■第IV編 ガラスの融液の性質
1 ガラス中の物質移動 [清水雅弘]
1.1 ガラス融液中の物質拡散
1.1.1 自己拡散
1.1.2 相互拡散
1.2 拡散現象と融液への影響
1.3 中性分子の拡散
1.4 イオンの拡散
1.4.1 ナトリウムイオンの自己拡散係数の組成依存性
1.4.2 ガラス融液における混合アルカリ効果
1.4.3 イオン交換
1.4.4 ソレー効果(温度勾配下でのイオン拡散)
2 粘 度 [武部博倫]
2.1 ガラスの粘性挙動および粘弾性挙動
2.2 粘度測定法
2.3 粘性流動
2.4 ガラス組成と粘度
3 結晶化 [本間 剛]
3.1 ガラスの結晶化に関する背景
3.2 結晶化の理論
3.2.1 核形成
3.2.2 結晶成長
3.3 熱履歴と結晶化ガラスの形態
3.4 結晶化に関する測定方法
3.4.1 熱分析
3.4.2 X線回折法
3.4.3 分光法
3.3.4 顕微鏡観察
4 分 相 [大幸裕介]
4.1 分相の理論
4.1.1 相図と自由エネルギー
4.1.2 分相後のガラス組成の計算
4.2 分相機構
4.2.1 核生成―成長機構による分相
4.2.2 スピノーダル分解機構による分相
4.2.3 結晶化および副成分の添加効果
4.2.4 固体NMR分光法
5 表面張力 [藤野 茂,助永壮平]
5.1 表面と表面張力
5.2 表面張力測定方法
5.2.1 リング引上げ法
5.2.2 最大泡圧法
5.2.3 液滴振動法
5.3 測定値と組成
5.3.1 実測データの紹介
5.3.2 組成からの推算式
5.4 工学的意味
5.4.1 組成からの推算式
6 密 度 [藤野 茂,徳永博文]
6.1 密度からの物性値
6.2 密度の測定法
6.2.1 アルキメデス2球法
6.2.2 セシルドロップ法(静滴法)
6.2.3 浮遊法
6.3 代表的な測定例
6.3.1 密度の組成依存性
6.3.2 密度の温度依存性
6.4 密度推算の試み
7 比熱・熱容量 [菅原 透]
7.1 比熱・熱容量の測定法
7.1.1 示差走査熱測定
7.1.2 落下法熱量測定
7.2 ガラス組成と比熱
7.2.1 ケイ酸塩融体の熱容量(Al2O3,B2O3を含まないとき)
7.2.2 アルミノケイ酸塩融体とホウケイ酸塩融体の熱容量
8 熱伝達 [齊藤敬高]
8.1 熱伝導と放射熱伝導
8.2 熱伝導率の測定法
8.2.1 非定常法
8.2.2 定常法
8.3 熱伝導率の組成依存性
9 電気伝導度 [吉田紀之]
9.1 ガラス融液の電気伝導度
9.2 電気伝導度の測定方法
9.3 電気伝導度の温度・周波数依存性
9.3.1 温度依存性
9.3.2 周波数依存性
9.4 電気伝導度の組成依存性
9.4.1 アルカリイオン伝導性
9.4.2 混合アルカリ効果
9.4.3 無アルカリガラス
10 酸度・塩基度 [菅原 透]
10.1 酸化物融体の酸・塩基反応と酸度・塩基度
10.2 酸化物融体の重合・解重合反応と塩基度
10.3 相平衡解析による架橋酸素活量と塩基度の見積もり
10.4 電気化学測定による塩基度の見積もり
10.4.1 Na2O活量の起電力測定
10.4.2 遷移金属イオンの酸化還元平衡のボルタンメトリー測定
11 酸化・還元 [徳永博文]
11.1 酸化・還元平衡
11.2 酸化・還元状態の評価方法
11.2.1 ボルタンメトリー
11.2.2 高温DXAFS測定
■第V編 ガラスと水
1 ガラス中の水(存在状態) [小池章夫]
1.1 分子状の水(H2O)と水酸基(OH)
1.2 水の溶解度
2 水が含まれるプロセス
2.1 ガラス作製時における水の侵入
2.2 水の拡散
3 評価方法
3.1 赤外分光法による水の分析
3.2 二次イオン質量分析法による水の分析
3.3 核磁気共鳴法による水の分析
3.4 核反応分析による水の分析
4 物性に与える影響
4.1 ガラス転移点,粘性と緩和挙動に与える影響
4.2 機械的特性に与える影響
4.3 化学的特性に与える影響
4.4 光学的特性に与える影響
4.5 電気的特性に与える影響
4.6 結晶化,分相に与える影響
■第VI編 ガラスの物性・構造シミュレーション
1 加成則 [徳田陽明]
1.1 Hugginsの方法
1.2 Appenの方法
1.3 Youngの方法
1.4 Bottingaの方法
1.5 補 足
2 データベースからの物性予測
2.1 データベース
2.2 INTERGLAD
2.2.1 INTERGLADの利用方法
2.2.2 組成と物性の関係の表示(三角プロット)
2.3 重回帰分析
2.3.1 重回帰分析による予測方法
2.3.2 INTERGLADを使った物性予測の例
3 機械学習による物性予測
3.1 機械学習の定義
3.2 機械学習の機能
3.3 機械学習の学習パターン
3.4 機械学習のアルゴリズム
3.4.1 最小二乗法
3.4.2 重回帰分析
3.4.3 ノンパラメトリックな回帰
3.5 交差検証
4 熱力学データベース [菅原 透]
4.1 CALPAHD法による熱力学解析
4.2 酸化物融体の熱力学的データベース
4.3 熱力学データベースの利用
5 構造シミュレーション [紅野安彦]
5.1 古典分子動力学法
5.2 第一原理分子動力学法
5.3 モンテカルロ法と逆モンテカルロ法
■第VII編 ガラス溶融の科学
1 ガラス化反応 [土井洋二]
1.1 バッチ溶融の全体像
1.2 融液の生成
1.2.1 原料の初期反応
1.2.2 溶融助剤の役割
1.3 融液中への固体の溶解
1.3.1 ガラス融液への固体粒子の溶解モデル
1.3.2 バッチフリータイム
1.4 バッチ山の溶融挙動
1.4.1 バッチ山内部の伝熱
1.4.2 バッチの溶解熱量
1.4.3 バッチの体積変化と直接観察試験
1.4.4 昇温過程のラフメルトの粘性
1.5 ガラス溶融炉におけるバッチの溶融
1.6 現状課題と今後の研究要素
2 清澄とガスの溶存濃度 [前原輝敬]
2.1 ガラス融液中の溶存ガス
2.1.1 物理溶存ガス
2.1.2 化学溶存ガス
2.2 ガラス融液中の気泡
2.2.1 原料溶解時に発生する泡
2.2.2 ガラス融液からのリボイル泡
2.2.3 ガラス融液と炉壁界面で発生する泡
2.2.4 ガラス融液中の異物から発生する泡
2.3 清澄の原理
2.4 清澄反応
2.4.1 酸素清澄
2.4.2 硫酸塩清澄
2.4.3 食塩清澄
3 均質化 [黒木有一]
3.1 均質性測定法
3.1.1 干渉計法
3.1.2 シュリーレン法(別名ナイフエッジテスト)
3.1.3 シャドウグラフ法
3.1.4 画像処理法
3.1.5 比重分散法
3.1.6 シェリュプスキー法
3.1.7 LFB-UMC法
3.2 均質化技術
3.2.1 不均質部分生成原因
3.2.2 攪拌による均質化
4 飛散と蒸発 [前原輝敬]
4.1 原料バッチからの飛散
4.1.1 原料粒子の粒度分布による影響
4.1.2 原料粒子の分解挙動による影響
4.2 ガラス融液からの蒸発
4.2.1 蒸発を表す理論式
4.2.2 ガラス溶融炉における蒸発現象
5 ガラス溶融プロセスで生じる欠点と解析方法
[黒田隆之助,榎本高志]
5.1 はじめに
5.1.1 欠点について
5.1.2 起源の分類
5.1.3 欠点の分析手法
5.2 結晶質欠点
5.2.1 結晶質欠点の分類
5.2.2 結晶質欠点の起源推定
5.3 ガラス質欠点
5.3.1 ガラス質欠点の分類
5.3.2 ガラス質欠点の起源推定
5.4 気泡欠点
5.4.1 生成メカニズムによる分類
5.4.2 起源推定と典型的なガス組成
5.4.3 分析の留意点
5.5 欠点解析における今後の展望
■第VIII編 ガラスの製造
1 原料とバッチ調合
[吉村紘平,中濵克幸,三田村直樹]
1.1 ガラス用原料
1.1.1 主原料
1.1.2 副原料
1.2 原料選定,バッチ調合から投入まで
1.2.1 原料選定の基準
1.2.2 原料の受入れと貯蔵
1.2.3 バッチの調合と投入
1.3 今後と課題
2 溶融炉
2.1 燃焼型溶融炉
[山道弘信,櫛谷英樹,赤木亮介]
2.1.1 連続炉
2.1.2 燃焼方式:エンドポート炉とサイドポート炉
2.1.3 素地流れを制御する構造
2.1.4 熱エネルギー回収方式:蓄熱室と換熱器
2.1.5 燃料と燃焼
2.1.6 溶融炉の熱勘定
2.1.7 省エネルギーの変遷
2.2 機能分離型ガラス溶融炉 [向井隆司]
2.2.1 機能分離型ガラス溶融炉の構想
2.2.2 高速溶融技術
2.2.3 高速清澄技術
2.3 酸素燃焼 [金谷 仁]
2.3.1 酸素燃焼炉の特徴
2.3.2 酸素バーナー
2.3.3 酸素燃焼炉内雰囲気の変化とその影響
2.3.4 酸素燃焼の今後について
2.4 電気溶融 [金谷 仁]
2.4.1 直接通電加熱の分類
2.4.2 電極の選択
2.4.3 全電融炉の特徴
2.4.4 全電気溶融炉の設計
2.4.5 全電気溶融の今後
2.5 気中溶融 [大川 智]
2.5.1 気中溶融法の原理
2.5.2 造粒原料
2.5.3 気中における溶融・ガラス化
2.5.4 気中溶融炉
2.6 放射性廃棄物固化ガラス溶融炉
[薄井康史,坂井 彰,小池上 一]
2.6.1 放射性廃棄物固化ガラス溶融炉の特徴 [薄井康史,坂井 彰]
2.6.2 高レベル放射性廃棄物固化ガラス溶融炉
2.6.3 低レベル放射性廃棄物固化ガラス溶融炉[小池上 一]
3 溶融炉におけるガラス素地の流れ
[岩瀬世彦]
3.1 溶融炉内の化学現象,物理現象
3.1.1 溶融炉内の化学現象
3.1.2 溶融炉内の物理現象
3.2 溶融炉解析
3.2.1 模型実験(物理モデル,液体モデル)による素地流れ解析
3.2.2 CFDによる溶融炉解析
3.3 現状の課題と将来
4 耐火物
4.1 電鋳れんが [俣野健児]
4.1.1 電鋳れんがの特徴
4.1.2 電鋳れんがの種類
4.1.3 鋳造方法による製品分類
4.2 焼成れんが [寺牛唯夫]
4.2.1 ケイ石れんが
4.2.2 高アルミナ質,ムライト質および粘土質れんが
4.2.3 塩基性れんが
4.2.4 特殊焼成れんが
4.3 不定形耐火物
4.3.1 キャスタブル耐火物
4.3.2 スタンプ材および補修材
4.3.3 プレキャストブロック
4.3.4 耐火モルタル
4.4 耐火物の損傷 [井出智之]
4.4.1 部位別損傷機構
4.4.2 耐火物から発生するガラス欠点
5 ガラスの成形
5.1 成形の概要 [田中毅彦]
5.1.1 粘性
5.1.2 表面張力
5.1.3 結晶化と均質性
5.1.4 熱膨張係数と粘弾性
5.1.5 色調と輻射率
5.1.6 固着現象と離型力
5.1.7 今後の動向
5.2 フロート成形
[吉村紘平,中濵克幸,三田村直樹]
5.2.1 フロート法
5.2.2 フロート製造プロセス
5.2.3 フロート法の最近の進捗
5.3 ロールアウト成形
5.3.1 型板ガラス
5.3.2 網入板ガラス
5.3.3 磨き板ガラス
5.4 ダウンドロー成形 [水嶋康之]
5.4.1 スロットダウンドロー成形
5.4.2 フュージョンダウンドロー成形
5.5 ブロー成形 [牧野良之]
5.5.1 ブロー成形の特徴
5.5.2 ブロー成形工程
5.5.3 ブロー成形の課題
5.6 プレス成形 [松田哲也]
5.6.1 プレス成形の原理と特徴
5.6.2 ガラス食器のプレス成形
5.7 モールドプレス [白石幸一郎]
5.7.1 成形法
5.7.2 ガラスの種類と光学設計の広がり
5.7.3 プリフォーム
5.7.4 型材料と型加工
5.7.5 ガラス非球面レンズの用途
5.8 ガラス管成形 [伊澤誠一]
5.8.1 ダンナー法
5.8.2 ベロー法
5.8.3 ダウンドロー法
5.8.4 アップドロー法
5.8.5 ガラス管成形の課題と今後
5.9 リドロー成形 [田中宏和]
5.9.1 結晶化ガラスのリドロー成形
5.9.2 光学素子のリドロー成形
5.9.3 板ガラスのリドロー成形
5.10 ガラスの繊維化 [中村幸一]
5.10.1 長繊維
5.10.2 短繊維
6 徐 冷
6.1 徐冷の理論 [小池章夫]
6.1.1 徐冷の目的
6.1.2 ひずみの発生原因
6.1.3 ひずみの評価方法
6.1.4 徐冷によって変化する特性
6.1.5 徐冷スケジュール
6.2 熱収縮
6.2.1 熱収縮現象とは
6.2.2 熱収縮量の測定方法
6.2.3 熱収縮の低減方法
6.3 光学ガラスの屈折率制御 [上田 基]
6.3.1 ひずみによる屈折率変動と徐冷(アニール)
6.3.2 徐冷による屈折率調整
6.3.3 光学ガラスの徐冷の実際
■第IX編 ガラスの加工/表面処理
1 冷間加工
1.1 切 断 [留井直子,山本幸司]
1.1.1 スクライブ工程
1.1.2 ブレイク工程
1.1.3 砥粒加工による切断
1.2 研削加工 [伊藤正文]
1.2.1 研削加工プロセス
1.2.2 研削加工後の品質
1.2.3 現状の課題と今後の展開
1.3 研 磨 [伊藤正文,宮谷克明]
1.3.1 ラップ加工
1.3.2 ポリッシュ加工
1.4 穴あけ・溝形成 [伊藤正文]
1.4.1 穴あけ・溝形成
1.4.2 現状の課題と今後の展開
1.5 レーザー加工によるガラスの内部構造改質
[下間靖彦]
1.5.1 超短パルスレーザーによる内部構造改質の加工原理
1.5.2 内部構造改質とその応用事例
1.5.3 課題と今後の展開
1.6 化学処理
[齊藤俊介,新美伍郎,宮井佑介]
1.6.1 薬液によるガラス加工技術
1.6.2 無アルカリガラスの薄肉化加工
1.6.3 ガラスエッチング装置
1.6.4 今後取り組むべき課題
2 封着加工 [西川欣克]
2.1 封着とその機能
2.2 ガラス封着の要件
2.2.1 封着温度
2.2.2 ガラス内部の応力
2.2.3 界面反応と気密性
2.3 フリット封着
2.4 陽極接合
3 強 化
3.1 物理強化 [瀬戸啓充]
3.1.1 風冷強化の原理
3.1.2 風冷強化ガラスの特徴
3.1.3 物理強化ガラスの製造方法
3.1.4 欠陥検出・除去技術
3.2 化学強化 [林 和孝]
3.2.1 化学強化とは
3.2.2 化学強化による強度向上のメカニズム
3.2.3 化学強化に適したガラス
3.2.4 化学強化の方法
3.2.5 化学強化ガラスを用いた製品
3.2.6 化学強化ガラスのキャラクタリゼーション
3.2.7 今後の化学強化ガラスの展望
4 コーティング
4.1 ガラス上へのコーティング技術とその種類,今後の展開 [稲岡大介]
4.2 気相成膜法 [釣 慶子]
4.2.1 PVD法(物理蒸着法)
4.2.2 CVD法(化学蒸着法)
4.3 液相成膜法 [籔田武司]
4.3.1 ゾル-ゲル法による薄膜作製法
4.3.2 塗布法による成膜方法
4.3.3 その他の成膜方法(液相析出法)
4.3.4 課題と今後
■第X編 ガラスの製品
1 主要な工業的ガラス [前田 敬]
1.1 ガラス工業
1.1.1 ガラス工業の歴史
1.1.2 現代のガラス産業と今後の展望
2 建築用ガラス
2.1 建築用板ガラス [赤田修一]
2.1.1 外観による分類
2.1.2 光透過性能による分類
2.1.3 耐熱板ガラス
2.1.4 その他の特殊板ガラス
2.2 建築用加工ガラス [桶谷幸史]
2.2.1 合わせガラス
2.2.2 Low-Eガラス
2.2.3 複層ガラス
2.2.4 強化ガラス
2.2.5 倍強度ガラス
2.2.6 防火・耐火ガラス
2.3 ガラスブロック [桑原英一郎]
2.3.1 はじめに
2.3.2 意匠性
2.3.3 採光性
2.3.4 遮音性・断熱性
2.3.5 防火・耐火性
2.3.6 施工法
3 車両用ガラス
3.1 車両に用いられるガラス製品 [宮川博行]
3.1.1 自動車窓ガラス
3.1.2 構造材,電子機器,情報機器向けガラス
3.1.3 CASE時代に向けたガラスの将来性
3.2 自動車窓ガラス [森 雅明,竹内彰一]
3.2.1 合わせガラス[森 雅明]
3.2.2 強化ガラス
3.2.3 黒セラ
3.2.4 一体成形品
3.2.5 コーティング品
3.2.6 ガラスアンテナ[竹内彰一]
3.3 ガラス繊維 [大谷昌功]
3.3.1 エアインテークマニホールド
3.3.2 車載電子・電装部品
3.3.3 モジュール類(フロントエンド,バックドア)
3.3.4 内装天井材
3.3.5 構造部材
3.3.6 吸音・断熱材
3.4 各種デバイス用ガラス [長嶋達雄]
3.4.1 「connected」に寄与するガラス
3.4.2 「autonomous」に寄与するガラス
3.4.3 「electric」に寄与するガラス
3.4.4 「shared」その他に寄与するガラス
4 容器ガラス
4.1 び ん [和田 龍]
4.1.1 概 要
4.1.2 ガラスびんの性質
4.1.3 ガラスびんの製造方法
4.1.4 ガラスびんの軽量化
4.2 テーブルウェア [柴田憲章]
4.2.1 生産の概要
4.2.2 用途別の分類
4.2.3 ガラス組成
4.2.4 製造方法
4.2.5 規格と法律
5 理化学用ガラス
5.1 ホウケイ酸ガラス [桃井 弘]
5.1.1 化学分析用ガラス器具
5.1.2 ガラス製化学プラント
5.1.3 理化学用ガラス以外の分野への展開
5.2 高ケイ酸ガラス [水嶋康之]
5.2.1 製造方法と特性
5.2.2 機能性高ケイ酸ガラス
5.3 pHセンサー用ガラス [橋本忠範]
5.3.1 pH電極の基礎
5.3.2 pH電極の構成
5.3.3 新しいガラスpH電極
6 医療用ガラス
6.1 医薬品容器用ガラス
[長壽 研,新井 智]
6.1.1 医薬品容器用ガラスの種類
6.1.2 ガラス製医薬品容器の種類
6.1.3 ガラス製医薬品容器の加工
6.1.4 ガラス製医薬品容器の内面処理
6.1.5 ガラス製医薬品容器に求められる化学的耐久性
6.2 微小医療デバイス用ガラス
6.2.1 ガラス製マイクロ流体チップ
6.2.2 ガラス製フローリアクター
6.3 生体用ガラス
[横井太史,川下将一,大槻主税]
6.3.1 骨修復用ガラス
6.3.2 歯科用ガラス
6.3.3 がん放射線治療用ガラス
7 照明用ガラス
7.1 白熱電球用ガラス [山崎博樹]
7.1.1 一般照明用電球
7.1.2 自動車電球
7.1.3 ハロゲン電球
7.2 蛍光灯用ガラス
7.3 HIDランプ用ガラス
7.4 LED用ガラス [中山勝寿]
7.4.1 LED用波長変換材料
7.4.2 LED用高放熱ガラスセラミックス基板
7.5 OLED用ガラス [山崎博樹]
8 石英ガラス [横山 優]
8.1 原料と製造方法
8.1.1 原 料
8.1.2 製造方法
8.2 特 性
8.2.1 仮想温度
8.2.2 密 度
8.2.3 熱特性
8.2.4 光学特性
8.2.5 電気特性
8.2.6 化学特性
8.2.7 機械特性
8.3 用 途
8.3.1 紫外線用光学部材
8.3.2 光ファイバー
8.3.3 その他の光学部材
8.3.4 照明管
8.3.5 液晶ディスプレイ基板
8.3.6 半導体プロセス用部材
8.3.7 単結晶引上げ用るつぼ
8.3.8 ヒーター管
8.3.9 バイオチップなど
9 エレクトロニクス用ガラス
9.1 ディスプレイ用ガラス [林 和孝]
9.1.1 電子ディスプレイとガラス
9.1.2 電子ディスプレイ技術の概要
9.1.3 ディスプレイ基板としてのガラスの特長
9.1.4 アクティブマトリクス型ディスプレイ用基板ガラス
9.1.5 ディスプレイ用ガラス基板の動向
9.1.6 フレキシブルディスプレイ製造用キャリア基板
9.2 ディスプレイ用カバーガラス(化学強化)
[林 和孝]
9.2.1 カバーガラスへの化学強化ガラスの応用
9.2.2 カバーガラスの動向
9.2.3 カバーガラスの評価方法
9.3 磁気ディスク用ガラス [江田伸二]
9.3.1 磁気ディスク用ガラスの必要特性
9.3.2 熱アシスト記録用ガラス基板
9.3.3 多数枚搭載用高剛性ガラス基板
9.3.4 高記憶容量HDDにおけるガラス基板
9.4 マスク基板用ガラス [尾上貴弘]
9.4.1 材料要求特性とその変遷
9.4.2 ガラス材料の種類と特徴
9.4.3 今後の動向
9.5 電子部品用粉末ガラス [西川欣克]
9.5.1 封着用ガラス
9.5.2 厚膜形成用ガラスペースト
9.5.3 半導体被覆用ガラス
9.5.4 多層基板用ガラス
9.5.5 バインダー用ガラス
10 ガラス繊維 [中村幸一]
10.1 ガラス長繊維
10.1.1 Eガラス長繊維
10.1.2 特殊組成ガラス長繊維
10.1.3 特殊形状長繊維
10.2 ガラス短繊維
10.2.1 ガラス短繊維の組成と特性
10.2.2 ガラス短繊維の性能
10.2.3 ガラス短繊維の用途
11 特殊形状ガラス
11.1 フレーク [藤原浩輔]
11.1.1 ガラス組成と特性
11.1.2 フレークの製造
11.1.3 フレークの性質と用途
11.2 ガラスビーズ
[森田好輝,酒井智弘,東 賢志]
11.2.1 ガラスビーズの特性[森田好輝]
11.2.2 ガラスビーズの製造方法
11.2.3 ガラスビーズの種類と用途
11.2.4 湿式法によるガラスビーズ[酒井智弘,東 賢志]
11.3 ガラスフィルム [長谷川義徳]
11.3.1 ガラスフィルムの特長
11.3.2 ガラスフィルムの製法
11.3.3 ガラスフィルムの用途
11.4 多孔質ガラス [赤井智子]
11.4.1 多孔質ガラスの特徴
11.4.2 多孔質ガラスの製法
11.4.3 多孔質ガラスの応用
12 光学ガラス [立和名一雄]
12.1 光学ガラスの特徴
12.1.1 光学ガラスと光学設計
12.1.2 光学特性と分類
12.2 組 成
12.2.1 主要特性と組成の関係
12.2.2 硝種別組成概要
12.2.3 新光学ガラス
12.3 製 造
12.4 規 格
13 赤外線透過ガラス [佐藤史雄]
13.1 赤外線透過ガラスの用途
13.2 赤外線の透過原理
13.3 遠赤外線透過ガラス
13.3.1 カルコゲナイドガラス
13.3.2 カルコハライドガラス
13.4 中赤外線透過ガラス
13.4.1 ゲルマン酸塩系ガラス
13.4.2 アルミン酸塩系ガラス
14 光ファイバおよび光ファイバ関連製品
14.1 光ファイバ [齋藤和也]
14.1.1 光ファイバの構造と光伝送特性
14.1.2 光ファイバ材料
14.1.3 光ファイバ紡糸
14.1.4 光ファイバの用途
14.2 光導波路デバイス [長谷川和男]
14.2.1 光導波の基礎
14.2.2 石英PLC
14.2.3 プラズモン導波路
14.2.4 シリコンフォトニクス
14.3 光通信用ガラス部材 [田中宏和]
14.3.1 パッシブ光部品用ガラス部材
14.3.2 アクティブ光部品用ガラス部材
14.3.3 光ファイバー接続用ガラス部材
14.4 レーザーガラス
[齋藤和也,長谷川和男]
14.4.1 ファイバレーザー用ガラス
14.4.2 ファイバレーザーの利用(レーザー加工)
15 着色ガラス [立和名一雄]
15.1 光の吸収と色調
15.1.1 ガラスの色
15.1.2 着色ガラスの色表示方法
15.2 フィルターガラス
15.2.1 紫外透過フィルター
15.2.2 紫外吸収フィルター
15.2.3 シャープカットフィルター
15.2.4 赤外透過フィルター
15.2.5 青フィルター
15.2.6 緑フィルター
15.2.7 色温度変換フィルター
15.2.8 色補正シアンフィルター
15.2.9 ニュートラルデンシティーフィルター
15.2.10 赤外(熱線)吸収フィルター
15.2.11 波長校正フィルター
16 結晶化ガラス
16.1 ゼロ膨張結晶化ガラス [中根慎護]
16.1.1 ゼロ膨張の原理
16.1.2 組成と各成分の役割
16.1.3 製造方法
16.1.4 特徴と応用
16.1.5 最近の開発品
16.2 感光性ガラス [水嶋康之]
16.2.1 感光着色ガラス
16.2.2 感光化学切削ガラス
16.2.3 ポリクロマテックガラス
16.2.4 フォトクロミックガラス
16.2.5 偏光ガラス
16.3 マシナブルガラス [水嶋康之]
16.3.1 マシナブル結晶化ガラス
16.4 壁材用結晶化ガラス [中根慎護]
16.4.1 組成と製造方法
16.4.2 製品特性
16.4.3 施工法
16.4.4 集積法の意匠性
16.4.5 環境対応
17 放射線用ガラス
17.1 放射線遮蔽用ガラス [長壽 研]
17.1.1 放射線とその遮蔽
17.1.2 放射線遮蔽用ガラス
17.1.3 放射線の物質中での減衰と相互作用
17.1.4 放射線遮蔽用ガラスの板厚設計
17.1.5 放射線遮蔽用ガラスの耐候性
17.1.6 放射線着色
17.1.7 原子力用放射線遮蔽窓
17.2 放射線線量計用ガラス [池上 徹]
17.2.1 ガラス線量計の原理
17.2.2 ガラス線量計の特徴
17.2.3 ガラス線量計用ガラス素子の組成
18 ほうろう [若杉 隆]
18.1 ほうろう
18.1.1 概 要
18.1.2 構 造
18.1.3 ほうろう化過程
18.1.4 ほうろうの密着機構
18.1.5 フリット
18.1.6 ほうろうの評価方法
18.1.7 ほうろうの欠点
18.1.8 ほうろうの製造工程
18.1.9 ほうろうへの現在の装飾手法
18.2 グラスライニング
18.2.1 グラスライニングとほうろうの違い
18.2.2 製造方法
18.2.3 性質
18.2.4 用途
18.2.5 補修方法
19 薄膜コートガラス
19.1 透明導電膜 [田中 智]
19.1.1 透明導電膜の機能と用途
19.1.2 透明導電膜の種類
19.1.3 ITO膜
19.1.4 FTO膜
19.1.5 その他の透明導電膜
19.2 光学薄膜 [稲岡大介]
19.2.1 低反射ガラス(反射防止膜)
19.2.2 Low-Eガラス
19.2.3 高反射ガラス
19.3 表面改質薄膜 [籔田武司]
19.3.1 親水性コーティング
19.3.2 撥水性コーティング
19.3.3 抗菌・抗ウイルスコーティング
19.4 高機能コートガラス [金井敏正]
19.4.1 高性能コーティング付きガラス
19.4.2 複合機能コーティング付きガラス
19.5 干渉フィルター [真垣葉子]
19.5.1 ファブリー-ペロ型干渉フィルターの原理
19.5.2 金属膜使用干渉フィルター
19.5.3 誘電体多層膜干渉フィルター
19.5.4 高難易度フィルターの紹介
19.5.5 干渉フィルターの使用上の注意
20 電池用ガラス [林 晃敏,作田 敦]
20.1 全固体電池の特徴
20.1.1 全固体リチウム電池の特徴
20.1.2 全固体ナトリウム電池の特徴
20.2 ガラス電解質
20.3 電解質の評価方法
20.3.1 導電率
20.3.2 機械的性質
20.3.3 電気化学安定性
20.4 全固体電池の作製と評価
20.4.1 電極活物質
20.4.2 全固体電池の作製方法
20.4.3 固体界面の形成プロセス
21 特殊組成ガラス
21.1 フッ化物ガラス [沢登成人]
21.1.1 フッ化物ガラスの組成とガラス構造
21.1.2 フッ化物ガラスの製法
21.1.3 フッ化物ガラスの特徴的機能と応用
21.2 リン酸塩ガラス [正井博和]
21.2.1 リン酸塩ガラスの基礎
21.2.2 リン酸塩ガラスの応用
21.2.3 リン酸塩結晶化ガラス
21.3 フツリン酸塩ガラス [八田幹男]
21.3.1 蛍石レンズ代替
21.4 無容器法で合成できるガラス
[増野敦信]
21.4.1 無容器法
21.4.2 構 造
21.4.3 光学特性
21.4.4 発光特性
21.4.5 磁 性
21.4.6 機械特性
21.4.7 準安定相結晶化
21.5 テルライトガラス [岸 哲生]
21.5.1 テルライトガラスの特徴
21.5.2 テルライトガラスの物性
21.5.3 テルライトガラスの応用
21.6 混合アニオンガラス [瀬川浩代]
21.6.1 オキシナイトライドガラス
21.6.2 オキシカーバイドガラス
■第XI編 ガラスと環境
1 ガラスと環境 [赤井智子]
1.1 21世紀におけるエネルギー・環境問題
1.2 ガラス分野における環境問題
1.2.1 ガラス産業におけるCO2排出削減
1.2.2 ガラスと資源循環
1.2.3 ガラス産業における化学物質リスク管理
1.2.4 ガラスによる廃棄物固化
1.3 総括と今後の展望
2 ガラスリサイクル
2.1 ガラスリサイクル概論 [稲野浩行]
2.1.1 ガラスリサイクルの状況変化
2.1.2 ガラスリサイクルの条件
2.1.3 具体例
2.1.4 課題と今後の展望
2.2 ガラスびんのリサイクル [辻 良太]
2.2.1 ガラスびんのReduce(軽量化)
2.2.2 ガラスびんのReuse(再使用)
2.2.3 ガラスびんのRecycle(再生利用)
2.2.4 ガラスびん3Rの将来
2.3 グラスウールにおけるリサイクル技術
[関根圭二,沖村祥彦]
2.3.1 グラスウールの環境価値
2.3.2 グラスウールのリサイクルフロー
2.3.3 グラスウールの製造におけるリサイクル技術
2.3.4 グラスウールと今後のリサイクル技術
3 有害物質低減,代替ガラス
3.1 化学物質規制動向 [今井克彦]
3.1.1 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
3.1.2 化学物質排出把握管理促進法(化管法)
3.1.3 GHS
3.1.4 RoHS指令
3.1.5 REACH規則
3.2 代替ガラス
3.2.1 電子部品用ガラス[西川欣克]
3.2.2 光学ガラス[上原 進]
3.3 製造プロセスでの有害物質削減
[山本 柱]
3.3.1 環境関連法の体系
3.3.2 環境負荷物質
3.3.3 有害物質低減技術
3.3.4 今後の展望
4 放射性廃棄物固化ガラス
4.1 放射性廃棄物固化ガラス
[矢野哲司,坂井 彰]
4.1.1 放射性廃棄物の発生
4.1.2 使用済燃料の処理
4.1.3 放射性廃棄物のガラス固化
4.1.4 ガラス固化体,ガラス固化プロセスが備えるべき特徴
4.1.5 固化ガラスの種類
4.2 ガラス固化技術 [坂井 彰]
4.2.1 廃棄物元素の制御に関わる技術
4.2.2 今後の課題および展開
4.3 ガラス固化体の地層処分 [松原竜太]
4.3.1 地層処分の基本概念
4.3.2 地層処分時のガラス固化体の性能評価
5 持続可能社会に貢献するガラス
5.1 高断熱・高遮熱窓ガラス [平島重敏]
5.1.1 Low-E複層ガラスと建築物省エネ法
5.1.2 Low-E複層ガラスを用いた建物の省エネルギー性能
5.1.3 高性能窓システムを用いた建物の省エネルギー性能
5.1.4 ダイナミックウィンドウ
5.2 太陽電池用ガラス [黒岩 裕]
5.2.1 緒 言
5.2.2 太陽光発電の普及
5.2.3 太陽光発電の環境への貢献
5.2.4 太陽電池とガラス
5.2.5 ソーダ石灰ガラスの透過率向上
5.2.6 環境に対する太陽電池用ガラスの課題
5.2.7 結 言
5.3 グラスウール [中村幸一]
5.3.1 グラスウールと環境
5.4 強化ガラス繊維 [大谷昌功]
5.4.1 自動車軽量化用材料
5.4.2 風力発電風車ブレード
5.4.3 軽量構造材料
付 録
索 引
資 料 編

執筆者紹介
■編集委員
矢野哲司 東京科学大学
松岡 純 滋賀県立大学
中尾泰昌 前 AGC(株)
山本 茂 前 日本電気電子(株)
■編集参与
服部明彦 前 日本板硝子(株)
■執筆者(五十音順)
赤井智子 産業技術総合研究所
赤木亮介 AGC(株)
赤田修一 AGC(株)
新井 智 日本電気硝子(株)
池上 徹 前 AGCテクノグラス(株)
伊澤誠一 日本電気硝子(株)
井出智之 AGCセラミックス(株)
伊藤正文 AGC(株)
稲岡大介 日本板硝子(株)
稲野浩行 北海道立総合研究機構エネルギー・環境・地質研究所
稲葉誠二 AGC(株)
井上博之 東京大学
今井克彦 前 日本電気硝子(株)
岩瀬世彦 日本板硝子(株)
上田純平 北陸先端科学技術大学院大学
上田 基 (株)ニコン
上原 進 (株)オハラ
薄井康史 (株)IHI
江田伸二 HOYA(株)
榎本高志 AGC(株)
大川 智 AGC(株)
大窪貴洋 千葉大学
大谷昌功 日本電気硝子(株),Nippon Electric Glass Europe GmbH
太田弘道 茨城大学
大槻主税 名古屋大学
沖村祥彦 旭ファイバーグラス(株)
桶谷幸史 AGC(株)
小野正靖 日本電気硝子(株)
尾上貴弘 HOYA(株)
小野寺陽平 物質・材料研究機構マテリアル基盤研究センター
梶原浩一 東京都立大学
加藤嘉成 日本電気硝子(株)
角野広平 前 京都工芸繊維大学
金井敏正 前 日本電気硝子(株)
金谷 仁 日本電気硝子(株)
川下将一 東京科学大学
岸 哲生 東京科学大学
北村直之 産業技術総合研究所,(株)大興製作所
櫛谷英樹 AGC(株)
栗山延也 セントラル硝子(株)
黒岩 裕 AGC(株)
黒木有一 (公財)日本セラミックス協会,前 AGC
黒田隆之助 AGC(株)
桑原英一郎 日本電気硝子(株)
小池章夫 AGC(株)
小池上 一 (株)IHI
斎藤 全 愛媛大学
齋藤和也 豊田工業大学
齊藤俊介 (株)NSC
齊藤敬高 九州大学
坂井 彰 日本原燃
酒井智弘 AGC(株)
作田 敦 大阪公立大学
佐藤史雄 日本電気硝子(株)
沢登成人 (株)住田光学ガラス
篠崎健二 産業技術総合研究所
柴田憲章 前 東洋佐々木ガラス(株)
柴田浩幸 東北大学
清水雅弘 京都大学
下間靖彦 京都大学
白石幸一郎 HOYA(株)
菅原 透 秋田大学
助永壮平 東北大学
瀬川浩代 物質・材料研究機構電子・光機能材料研究センター
関根圭二 前 旭ファイバーグラス(株)
瀬戸啓充 日本板硝子(株)
大幸裕介 名古屋工業大学
高石大吾 京都市産業技術研究所
高橋儀宏 岡本硝子(株)
竹内彰一 前 AGC(株)
竹中敦義 AGC(株)
武部博倫 愛媛大学
立和名一雄 HOYA(株)
田中毅彦 日本山村硝子(株)
田中宏和 日本電気硝子(株)
田中 智 日本板硝子(株)
長壽 研 日本電気硝子(株)
辻 良太 日本山村硝子(株)
釣 慶子 日本板硝子(株)
寺牛唯夫 ロザイ工業(株),前 AGCセラミックス(株)
寺門信明 京都大学
土井洋二 AGC(株)
徳田陽明 滋賀大学
徳永博文 AGC(株)
留井直子 三星ダイヤモンド工業(株)
長嶋達雄 AGC(株)
中根慎護 日本電気硝子(株)
中濵克幸 セントラル硝子プロダクツ(株)
中村幸一 日東紡績(株)
中山勝寿 AGC(株)
新美伍郎 (株)NSC
西川欣克 日本電気硝子(株)
西 剛史 茨城大学
橋本忠範 三重大学
長谷川和男 光産業創成大学院大学
長谷川義徳 前 日本電気硝子(株)
八田幹男 HOYA(株)
林 晃敏 大阪公立大学
林 和孝 AGC(株)
東 賢志 AGCエスアイテック(株)
平島重敏 AGC(株)
藤野 茂 九州大学
藤原浩輔 日本板硝子(株)
紅野安彦 岡山大学
本間 剛 長岡技術科学大学
前田 敬 AGC(株),東京理科大学
前原輝敬 AGC(株)
真垣葉子 (株)ニコン
牧野良之 東洋ガラス(株)
正井博和 産業技術総合研究所
増野敦信 京都大学
俣野健児 AGCセラミックス(株)
松田哲也 東洋佐々木ガラス(株)
松原竜太 原子力発電環境整備機構
水嶋康之 前 コーニングジャパン(株)
三田村直樹 セントラル硝子(株)
宮井佑介 NSC(株)
宮川博行 前 AGC(株)
宮宅ゆみ子 東京都立産業技術研究センター
宮谷克明 AGC(株)
向井隆司 AGC(株)
村上久美子 三星ダイヤモンド工業(株)
桃井 弘 AGCテクノグラス(株)
森 龍也 筑波大学
森田好輝 ユニチカガラスビーズ(株)
森 雅明 AGC(株)
矢野哲司 東京科学大学
籔田武司 日本板硝子(株)
山崎博樹 日本電気硝子(株)
山田明寛 滋賀県立大学
山田修史 産業技術総合研究所
山道弘信 AGC(株)
山本幸司 前 三星ダイヤモンド工業(株)
山本 柱 日本山村硝子(株)
山本雄一 AGC(株)
横井太史 東京科学大学
横山 優 クアーズテック合同会社
吉田紀之 日本電気硝子(株)
吉田 智 AGC(株)
吉村紘平 前 セントラル硝子(株)
若杉 隆 京都工芸繊維大学
和田 龍 前 日本山村硝子(株)