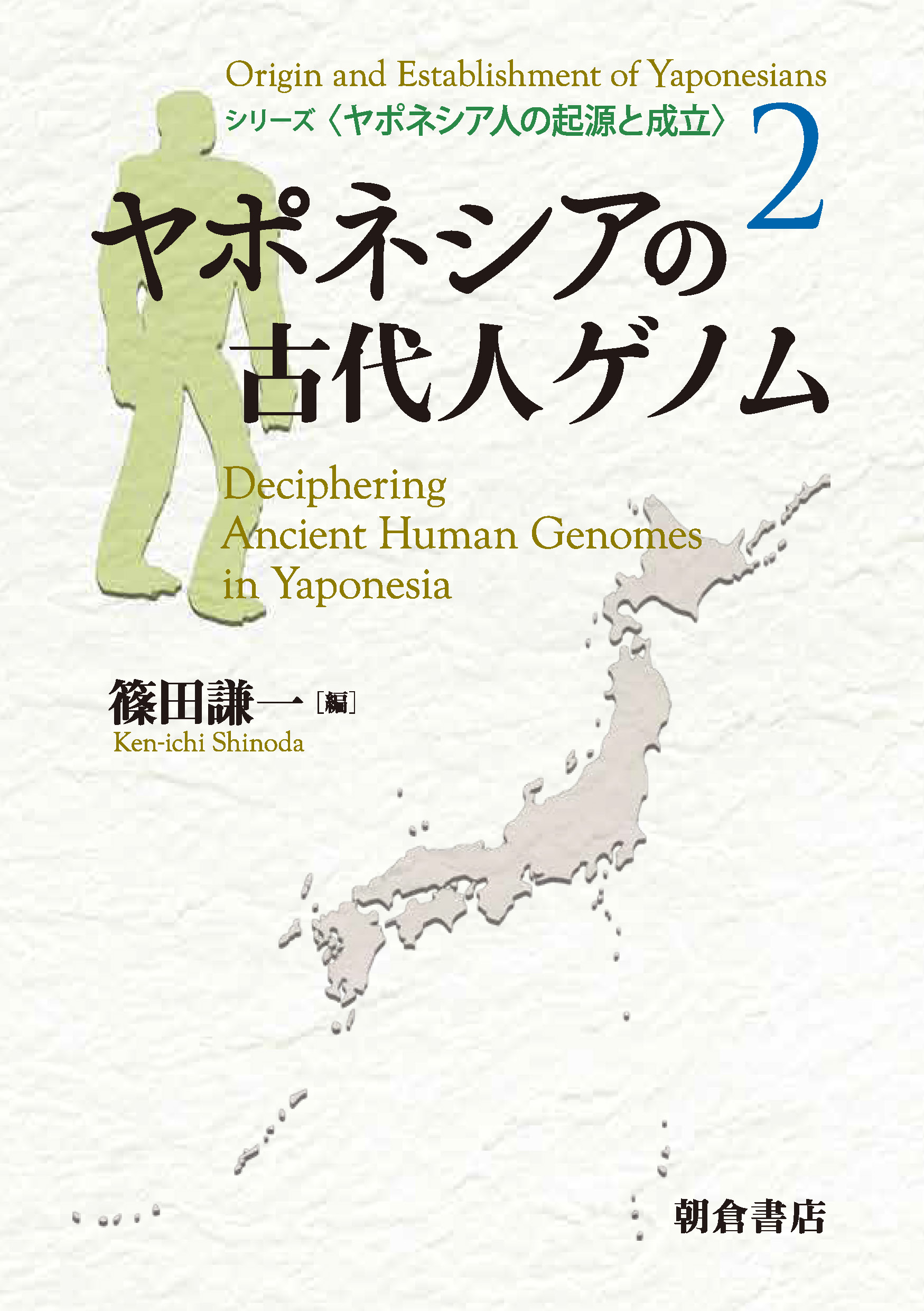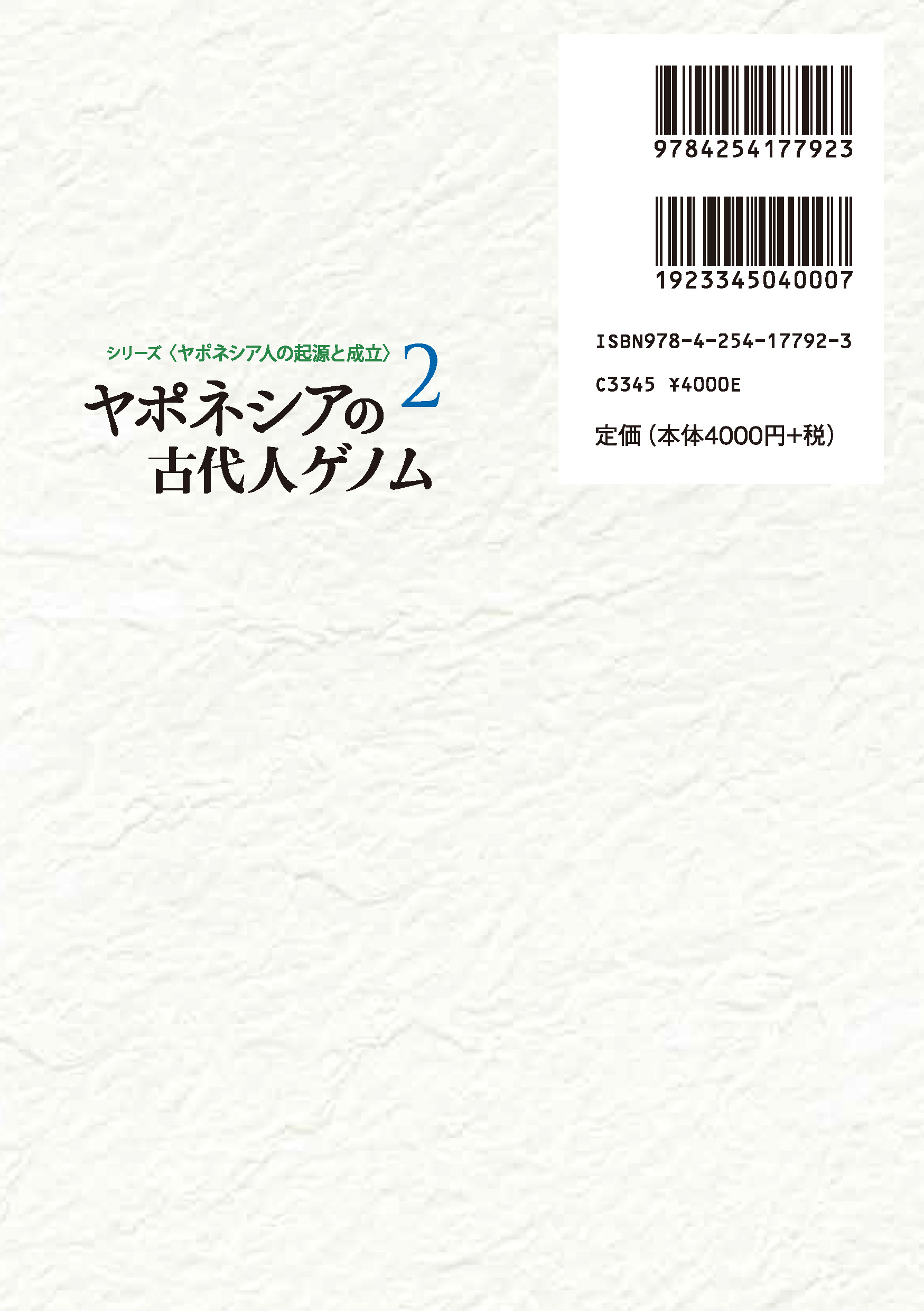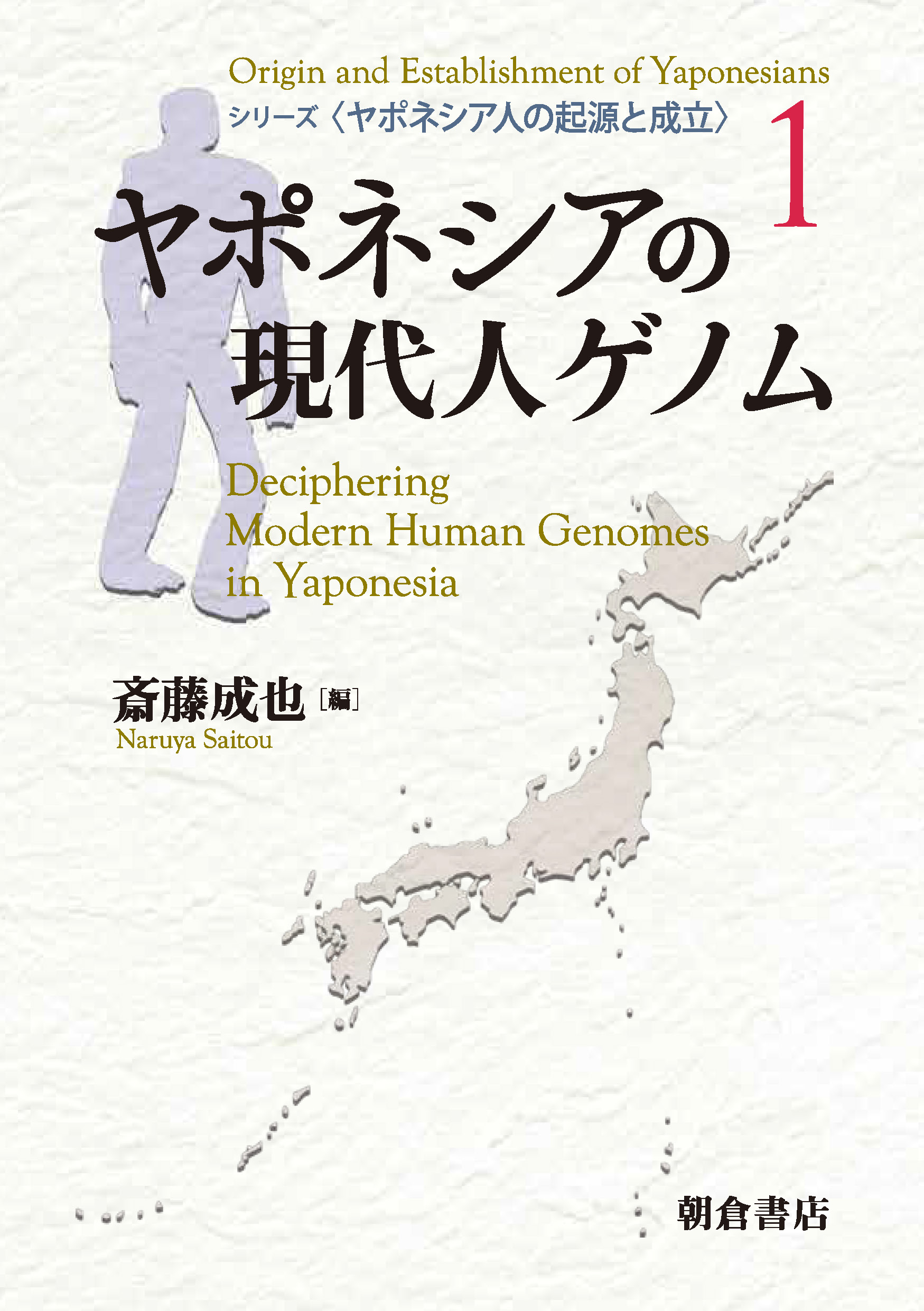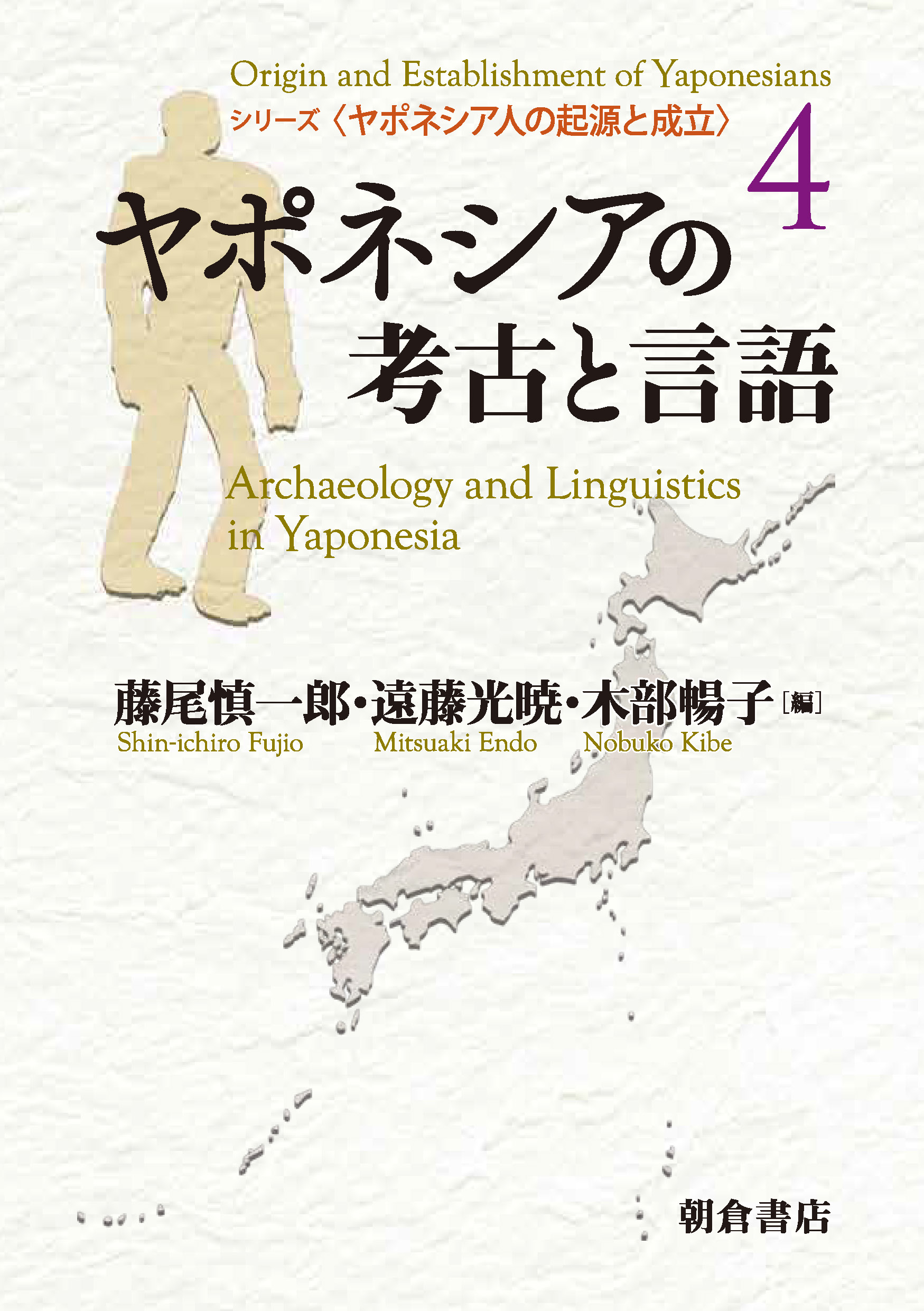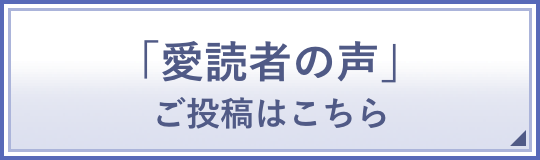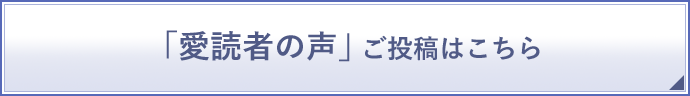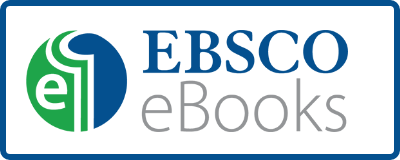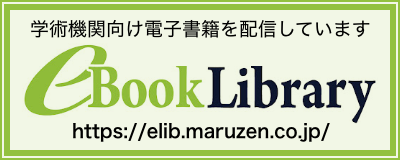BOOK SEARCH
シリーズ〈ヤポネシア人の起源と成立〉 2 ヤポネシアの古代人ゲノム
篠田 謙一(編)
内容紹介
歴史的に日本列島に居住していた人類集団,ヤポネシア人の起源と発展の歴史を紐解くシリーズ書。第2巻では古代ヤポネシア人を遺伝学的観点から解説。〔内容〕古代ゲノムから見た日本人の成り立ち(サピエンス史,港川人,古墳時代,オホーツク文化人)/古代ゲノム研究の展開(DNA,ウイルス,HLA,自然選択,タンパク質)
編集部から
序文より
古代の人骨やその他の生物由来の試料にわずかに残るDNA を分析の対象とする古代ゲノム研究は、1980 年代に人骨などの古代試料にもごくわずかなDNA が残っていることが明らかになったことを契機としてスタートした。特にコロナウイルスの検知のために利用されたことで知られるDNA の増幅技術であるPCR 法の発見は、この分野の研究を大きく推進させた。ただし、古代のサンプルに残るDNA は極めて微量で、2010 年頃までは、その解析は母系に遺伝するミトコンドリアDNA の分析にとどまっていた。しかし、2006 年に実用化が始まった画期的なDNA 解析機器である次世代シークエンサは、その状況を一変させることになった。
この機器を用いることで、古代試料であっても膨大な情報をもつ核ゲノムも解析の対象となり、現在ではサンプルによっては現代人と同じ精度でのゲノムの解析も可能になっている。(中略)
2022 年のノーベル生理学・医学賞は、古代ゲノム研究を最初期から牽引し、現在の成功までを一貫して主導した、ドイツのマックス・プランク進化人類学研究所のスバンテ・ペーボ博士に与えられている。このことは古代ゲノム研究が、単に古代試料に由来するDNA の分析技術として評価されたのではなく、そこから得られる知見が様々な学問分野に大きな影響を与え、新たな知の創造が期待できることにあるのだろう。
今世紀になってこの技術は従来の人類学の姿を大きく変えてきた。今後の日本の人類学研究も間違いなく、この技術が生み出す知見によって、新たなステージに進んでいくことになるはずだ。本書は、この分野の研究の現時点での到達点を示すものだが、今後の古代ゲノム研究がどのように発展していくのかを知ることのできる内容となっている。
目次
第Ⅰ部 古代ゲノムから見た日本人の成り立ち
第1章 古代ゲノム研究―概論およびヤポネシア人と大陸の関係― 〔篠田謙一〕
1.1 古代ゲノム研究概説
1.2 日本列島集団の分析の歴史
1.3 ヤポネシアと大陸との関係
1.4 大陸での集団の形成と日本列島人
第2章 古代ゲノムが書き替えたサピエンス史 〔太田博樹〕
2.1 古代ゲノムの“価値”
2.2 過去30 年で書き替えられたサピエンス史
2.3 私たちはいつから“ヒト”なのか?
2.4 ネアンデルタール人のゲノム解析
2.5 東ユーラシア大陸への拡散
第3章 港川人のミトコンドリアゲノム解析 〔五條堀 淳・水野文月〕
3.1 琉球列島における旧石器時代の人骨
3.2 港川人のDNA 分析
3.3 港川1号人骨のmtDNAハプログループとその系統
3.4 ネットワーク系統樹による解析
3.5 多次元尺度構成法(MDS)による解析
3.6 港川1号と後のヤポネシア集団とのつながり
3.7 他の地域との比較から
第4章 古代人のミトコンドリアゲノム解析 〔安達 登〕
4.1 ミトコンドリアDNAと系統分類
4.2 日本列島人のミトコンドリアDNAの特徴とその変遷
第5章 古代人ゲノムから見た弥生・古墳時代の集団形成史 〔神澤秀明〕
5.1 はじめに
5.2 形態学からゲノムの時代へ
5.3 ゲノムが語る多様な弥生時代人
5.4 渡来系弥生人の源流
5.5 渡来系弥生人の拡大
5.6 混血の進む古墳時代人
5.7 今後の課題と展望
第6章 オホーツク文化人のゲノム解析 〔佐藤丈寛〕
6.1 オホーツク文化の特徴
6.2 オホーツク文化とアイヌ文化
6.3 礼文島浜中2遺跡とNAT002
6.4 NAT002のゲノム配列データとその真正性
6.5 NAT002とその他の北東アジア集団との遺伝的関係
6.6 NAT002の遺伝的特徴の成り立ち
6.7 3系統の混合年代の推定
6.8 オホーツク文化人とアイヌとの関係
6.9 骨過剰形成に対するNAT002の遺伝的脆弱性
6.10 おわりに
第Ⅱ部 古代ゲノム研究の展開
第7章 古代DNAの抽出、評価とその応用 〔角田恒雄〕
7.1 古代DNAと分析方法
7.2 古代DNA抽出のための資料選定と抽出
7.3 古代DNAの状態評価とミトコンドリアDNAハプログループの簡易判定
7.4 APLP法の応用― 熊本大学医学部所蔵古人骨の分析―
第8章 古代のウイルス 〔西村瑠佳・井ノ上逸朗〕
8.1 古代ウイルスの探索
8.2 日本の古代ウイルス
8.3 まとめと展望
第9章 古代人のHLA解析 〔細道一善〕
9.1 HLA遺伝子
9.2 古代人のHLA遺伝子
第10章 日本人が受けた自然選択―現代人・古代人ゲノムの解析から― 〔河田雅圭〕
10.1 日本人が受けた自然選択とは
10.2 現代日本人ゲノムを用いた自然選択の検出
10.3 古代人ゲノムを含めた自然選択の解析
10.4 自然選択は日本人の性質をどう変化させたのか
10.5 おわりに
第11章 古代タンパク質の分析 〔西内 巧〕
11.1 タンパク質とは
11.2 プロテオーム解析の進歩とパレオプロテオミクス
11.3 動物骨のコラーゲンタンパク質のトリプシン消化断片の解析(ZooMS)
11.4 考古試料におけるメタプロテオミクス
11.5 おわりに
索 引

執筆者紹介
■シリーズ監修者
斎藤成也 国立遺伝学研究所名誉教授
■編集者
篠田謙一 国立科学博物館
■執筆者(五十音順)
安達 登 山梨大学大学院総合研究部医学域
井ノ上逸朗 国立遺伝学研究所名誉教授
太田博樹 東京大学大学院理学系研究科
角田恒雄 山梨大学大学院総合研究部医学域
河田雅圭 東北大学教養教育院
神澤秀明 国立科学博物館生命史研究部
五條堀 淳 総合研究大学院大学統合進化科学研究センター
佐藤丈寛 琉球大学大学院医学研究科
篠田謙一 国立科学博物館
西内 巧 金沢大学疾患モデル総合研究センター
西村瑠佳 東京大学医科学研究所
細道一善 東京薬科大学生命科学部
水野文月 東邦大学医学部